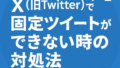「うちの子、どうしてこんなに勉強を嫌がるの?」と悩むお父さんお母さんは多いですよね。
でも、実はちょっとした工夫や声かけで、子どもは勉強への苦手意識を克服できるんです。この記事では、勉強嫌いな小学生でも楽しく学べる具体的な方法を、分かりやすくご紹介します。
ぜひ、子どもと一緒にチャレンジしてみてください!
小学生が勉強嫌いになる理由とは?
勉強が楽しくないと感じる瞬間
小学生が「勉強が嫌い!」と感じるとき、多くは「勉強が楽しくない」と思っている瞬間です。
たとえば、同じ内容の計算ドリルを何度も繰り返したり、分からない漢字を覚えるだけの勉強は、どうしても退屈に感じやすいものです。また、先生の説明が難しくて理解できないときや、テストで悪い点を取ってしまったときなど、自信をなくしてしまうこともよくあります。
こうした体験が重なると、「勉強=つまらないこと」というイメージが強くなり、自然と勉強から距離を置いてしまうのです。大人にとっては当たり前の勉強も、小学生にとってはまだまだ新しい世界。だからこそ、少しでも楽しいと感じられる工夫が大切です。
例えば、勉強の合間に好きなイラストを描いてみたり、先生や友達とおしゃべりしながら問題を解く時間を設けるだけでも、「勉強=つまらない」という気持ちはぐっと和らぎます。勉強が楽しいと感じる瞬間を増やすことが、苦手意識の克服には欠かせません。
わからないことが増えるとどうなる?
勉強で分からないことが増えてくると、子どもはどうしてもやる気をなくしてしまいがちです。
最初はちょっとした疑問でも、周りに質問しづらかったり、どこから手をつけていいか分からなくなったりして、そのまま放置してしまうことがよくあります。その結果、授業についていけなくなり、ますます勉強が苦手に感じてしまう悪循環に陥ります。
特に算数や国語などの基礎的な科目でつまずくと、次の単元も分からなくなってしまうので、わからないことはできるだけ早めに解決することが大切です。わからない部分は恥ずかしがらずに先生や家族に相談したり、友達同士で教え合うのもおすすめです。
また、最近はネットや動画などで簡単に解説を見ることもできるので、自分に合った方法で「わからない」を解消する習慣をつけましょう。わからないことが減ると、自然と勉強が楽しく感じられるようになります。
プレッシャーや比較のストレス
小学生は大人が思っている以上に「周りからのプレッシャー」や「他人との比較」に敏感です。
たとえば、テストの点数で友達や兄弟と比べられると、自分だけできないように感じて落ち込んでしまいます。また、「ちゃんと勉強しなさい」と言われ続けると、プレッシャーに押しつぶされてしまうこともあります。こうしたストレスが続くと、勉強そのものが嫌いになってしまうことがあるのです。
子ども一人ひとりには得意・不得意があるのが当たり前なので、他人と比べるよりも「前よりできるようになったね」と成長を褒めることが大切です。また、子どものペースに合わせて見守ってあげることで、プレッシャーから解放されて勉強に向かう気持ちが少しずつ育っていきます。
周りの友達の影響
学校生活で多くの時間を過ごす小学生にとって、友達の存在はとても大きなものです。
もし仲の良い友達が「勉強なんてつまらないよ」と言っていたら、自分も同じように感じてしまうことがあります。また、友達と遊ぶ時間が楽しいと、つい勉強よりも遊びを優先してしまうことも珍しくありません。
逆に、勉強を頑張る友達がいると「自分もやってみようかな」と思うきっかけにもなります。つまり、友達の言動や雰囲気が勉強への意識に大きな影響を与えているのです。友達と一緒に宿題をしたり、クイズ大会を開いたりすることで、「勉強=楽しい時間」という意識を自然と身につけることができます。周りの友達の良い影響を受けられる環境づくりも、勉強嫌いを克服するポイントです。
家庭の環境が与える影響
家庭での環境も、子どもの勉強に対する気持ちに大きく関わっています。
たとえば、テレビやゲームがずっとついていると、どうしても勉強に集中しづらくなります。また、家族が忙しくてなかなか勉強を見てあげられないと、子どもも「どうせ見てくれないし…」とやる気をなくしてしまうことがあります。
逆に、家族が一緒に勉強したり、「よく頑張ってるね」と声をかけてくれると、子どもも前向きな気持ちで勉強に取り組むようになります。特別なことをする必要はありません。子どもが勉強しているときに隣で本を読んだり、できたことを一緒に喜んだりするだけで、勉強に対する意識は大きく変わります。
家庭の温かいサポートがあれば、子どもは安心してチャレンジできるようになるのです。
勉強嫌い克服のための第一歩は「小さな成功体験」
簡単にできる目標の作り方
小学生が勉強嫌いを克服するためには、まず「簡単にできる目標」を作ることがとても大切です。
難しすぎる目標だと、途中で挫折してしまうことが多いからです。たとえば「今日は漢字を10個書けるようになる」「算数のドリルを3問だけ解く」など、子ども自身が「これならできそう!」と思えるような目標を設定しましょう。目標を達成できたら、しっかりと褒めてあげることもポイントです。
小さな達成感を積み重ねることで、少しずつ「勉強って意外とできるかも」と自信がついていきます。また、目標は毎日変えてもかまいません。飽きないようにいろいろな課題を設定するのも効果的です。簡単な目標をクリアする経験をたくさん積むことで、苦手意識は自然と薄れていきます。まずは「できること」を増やすことから始めましょう。
成功体験を積み重ねるコツ
成功体験を積み重ねるには、毎日の中で「できた!」と思える瞬間を増やすことが大切です。
例えば、1日5分だけでも勉強に取り組んでみる、わからなかった問題を1問だけ解けるようになるなど、ほんの些細なことでもOKです。その積み重ねが「自分にもできる!」という自信につながります。また、できたことを記録するのもおすすめです。カレンダーにシールを貼ったり、ノートに「できたことリスト」を書くことで、自分の成長を目で見て感じられるようになります。
さらに、家族や先生から「すごいね」「がんばったね」と声をかけてもらえると、やる気はますますアップします。大事なのは、完璧を目指すことではなく、昨日より少しだけ成長できた自分を認めることです。小さな成功体験を毎日積み重ねることで、勉強が嫌いだった子どもも、次第に勉強に対する苦手意識がなくなっていきます。
褒め方でやる気アップ
子どもは褒められることで、どんどんやる気が湧いてきます。
ですが、褒め方にもポイントがあります。たとえば、「すごいね!」とだけ言うよりも、「最後まで自分で解けてえらいね」「毎日コツコツ続けられているね」と、できた内容や努力した部分を具体的に褒めることで、子どもは自分の成長をしっかり実感できます。
また、結果よりも過程を褒めることが大切です。たとえテストの点数があまり良くなくても、「わからないところを一生懸命調べたんだね」「あきらめずに取り組めてすごいね」と声をかけてあげることで、自信につながります。
褒めることを通じて、子どもは「また頑張ろう!」という前向きな気持ちになれるのです。
失敗したときのフォロー方法
どんなに頑張っても、うまくいかない日もあります。
そんなときは「できなかったね」と責めるのではなく、「今日はちょっと難しかったね。でも次はきっとうまくいくよ」と励ましてあげましょう。また、失敗した理由を一緒に考えるのも大切です。
「どこでつまずいたのかな?」「どうやったら次はできるかな?」と、子ども自身に考えさせることで、失敗を成長のきっかけに変えることができます。失敗を恐れずにチャレンジする気持ちを育てることで、子どもはどんどん前向きになっていきます。
失敗したときこそ、温かいフォローと励ましの言葉が、子どもを支える大きな力になります。
ご褒美の与え方と注意点
ご褒美はやる気を引き出すのにとても効果的ですが、与え方には少し注意が必要です。
たとえば、「勉強したらゲームをしていいよ」といった約束をすることで、最初はモチベーションが上がります。しかし、ご褒美ばかりに頼ってしまうと、「ご褒美がないと勉強しない」という習慣がついてしまうことも。ご褒美はあくまで「ちょっとした励まし」として使い、勉強そのものの楽しさを感じられるよう工夫しましょう。
また、勉強が終わったら一緒におやつを食べる、好きなアニメを一緒に観るなど、家族のコミュニケーションの時間にするのもおすすめです。ご褒美を上手に使って、無理なく勉強の習慣をつけていきましょう。
「遊び」を取り入れた楽しい勉強法
ゲーム感覚で覚えるコツ
勉強といえば「机に向かってノートとにらめっこ」というイメージがありますが、ゲーム感覚を取り入れるだけで、ぐっと楽しい時間に変わります。
たとえば、漢字や英単語を覚えるときにカードゲームを使ったり、タイマーを使って「制限時間内に何問解けるか」挑戦してみるのもおすすめです。ポイントは「楽しい!」と感じる工夫をたくさん取り入れることです。
正解した数だけシールを貼っていくゲームや、家族や友達と競争するクイズ大会も盛り上がります。ゲーム感覚で取り組むことで、勉強が「嫌なこと」から「楽しいこと」へと変わり、自然とやる気がアップします。自分に合ったゲームルールを作って、日々の勉強に取り入れてみましょう。
友達や家族と競争しながら学ぶ
勉強を一人で続けるのは、どうしても飽きやすくなります。
そんなときは、友達や家族と一緒に学ぶのがおすすめです。たとえば、宿題を一緒にやったり、問題を出し合ったりして、ちょっとした競争をしてみるのも効果的です。「今日は誰が一番早く計算できるかな?」など、ゲーム感覚で楽しく取り組むと、普段よりも集中できたり、やる気が続いたりします。
家族で問題を出し合うクイズ大会も、勉強が好きになるきっかけになるはずです。また、友達と協力して難しい問題に挑戦することで、自然とコミュニケーション能力も身につきます。一緒に学ぶ仲間がいると、勉強の楽しさや達成感も倍増します。
工作や実験で理科を好きに
理科が苦手な子どもでも、工作や実験を通して学ぶと、自然と興味がわいてきます。
たとえば、家にある材料で簡単なスライムを作ってみたり、紙飛行機を飛ばして空気の流れを観察したりするだけでも、理科の知識を楽しく身につけることができます。身近なものでできる実験や工作は、「どうしてこうなるの?」と好奇心を刺激し、知りたい気持ちを自然と引き出します。
親子で一緒に取り組むことで、家族のコミュニケーションも深まり、子どもは学ぶことの楽しさを実感できます。実験の結果をまとめたり、発表したりすることで、表現力や発想力も養われます。理科嫌いを克服する第一歩は、「体験する楽しさ」を知ることから始まります。
クイズやパズルで頭の体操
クイズやパズルは、遊びながら自然と頭を使うことができる最高の勉強法です。
たとえば、クロスワードパズルやナンプレ(数独)、しりとりゲームなどは、言葉や数字のセンスを楽しく身につけることができます。また、「今日は○問解けるかな?」と目標を決めて挑戦してみると、クリアしたときの達成感も大きくなります。家族みんなで楽しめるクイズ番組を観るのも、知識を広げる良いきっかけになります。
パズルやクイズは、集中力や発想力を鍛える効果もあるので、勉強嫌いな子どもにもぴったりです。毎日の生活の中に少しずつ取り入れて、頭の体操を楽しみながら勉強の力を伸ばしましょう。
スマホやタブレットの活用方法
最近は、スマホやタブレットを使った勉強法もとても人気です。
アプリや動画を使えば、ゲーム感覚で英単語や漢字を覚えたり、算数の問題にチャレンジできたりします。たとえば、YouTubeの勉強チャンネルや、アニメで学べる解説動画などは、子どもたちにも大好評です。
また、アプリを使って問題を解くと、すぐに答えが分かるので、間違えても「次は頑張ろう!」と前向きな気持ちになりやすいのが特徴です。ただし、使いすぎには注意しましょう。決まった時間だけ使う、勉強が終わったご褒美に使うなど、ルールを決めて上手に活用すれば、スマホやタブレットはとても心強い勉強の味方になります。
勉強習慣を身につけるには?
無理なく始める時間割の作り方
勉強を習慣にするには、「毎日同じ時間に少しずつ取り組む」ことが大切です。
でも、いきなり長い時間を勉強にあてると、続かなくなってしまいます。まずは「夕食の前に10分だけ」や「学校から帰ったらまず宿題をする」など、無理のないスケジュールを考えましょう。時間割を作るときは、子どもと一緒に相談しながら決めるのがポイントです。
好きなテレビ番組や遊ぶ時間も大事にしながら、勉強の時間をうまく組み込むことで、無理なく続けられるようになります。また、達成できた日はカレンダーに印をつけたり、シールを貼ったりすると、「今日もできた!」という実感が積み重なり、やる気もアップします。
時間割は、生活リズムを整えるだけでなく、自分で考えて計画を立てる力も身につけられるのでおすすめです。
勉強する場所の工夫
勉強に集中できる場所を作ることも大切です。
たとえば、リビングや自分の机など、子どもが落ち着いて取り組めるスペースを決めておきましょう。周りにテレビやおもちゃがあると気が散りやすいので、できるだけ余計なものは片付けておくと良いです。また、照明や椅子、机の高さなども、子どもが快適に感じるように整えてあげましょう。
家族が近くにいるリビングなら、質問もしやすくなりますし、「頑張ってるね」と声をかけてもらえるだけで励みになります。ときには、図書館やカフェなど普段と違う場所で勉強するのも新鮮で楽しい体験になります。勉強する場所を工夫することで、集中力がぐんと高まり、勉強へのハードルも下がります。
毎日続けるための「きっかけ」づくり
勉強を毎日続けるには、「きっかけ」を作ることが大切です。
たとえば、「おやつを食べたらすぐ勉強」「夕飯前の10分だけ勉強」など、日常の流れの中に勉強を組み込むと、無理なく続けやすくなります。また、「お気に入りのノートを使う」「好きな音楽を聴きながら」など、自分だけの勉強ルールを作るのも効果的です。
大切なのは、毎日「やらなきゃ」ではなく、「今日もやってみようかな」と思える仕掛けを作ることです。ちょっとした工夫で、勉強への気持ちは大きく変わります。小さな習慣を積み重ねることで、自然と勉強が生活の一部になり、無理なく続けられるようになります。
親子で一緒に取り組むポイント
親子で一緒に勉強に取り組むことで、子どもは安心してチャレンジできるようになります。
たとえば、親が隣で本を読んだり、分からないところを一緒に考えたりするだけでも、子どもは「一人じゃない」と感じて心強くなります。また、親自身が何かに挑戦している姿を見せることも、子どもにとっては良い刺激になります。
たとえば、親が趣味の勉強をしたり、仕事の資格試験の勉強をしたりする様子を見せるだけでも、「大人になっても勉強って大事なんだ」と思えるようになります。親子で一緒に頑張る時間を大切にして、お互いの成長を応援し合いましょう。
三日坊主にならないコツ
せっかく始めた勉強も、三日坊主で終わってしまうのはよくあることです。
続けるコツは、「無理をしないこと」と「楽しみながらやること」です。いきなり完璧を目指さず、できた日には自分をしっかり褒めてあげましょう。また、家族や友達に「毎日勉強を続けているよ」と報告することで、自然とモチベーションも上がります。
ときにはご褒美を用意したり、週末だけは好きな勉強だけをする「ごほうびデー」を作ったりするのもおすすめです。何より大切なのは、失敗しても「また明日から頑張ろう」と前向きに続けることです。コツコツ続けることで、いつの間にか勉強が習慣になっていきます。
親ができるサポートと声かけ
子どもを追い詰めない言葉
子どもが勉強を嫌いになる原因の一つに、親や先生からの「追い詰める言葉」があります。
「なんでできないの?」「また間違えたの?」といった言葉は、子どものやる気を大きく下げてしまいます。大切なのは、子どもが自分で頑張ろうと思えるような優しい言葉をかけることです。
たとえば、「よく頑張っているね」「少しずつできるようになっているよ」と前向きな言葉を選びましょう。また、ミスをしたときも「大丈夫、誰でも間違えるよ」と励ますことで、安心してチャレンジできるようになります。子どもは親の言葉にとても敏感なので、声かけ一つでやる気や自信が大きく変わります。
ポジティブなフィードバックの大切さ
子どもが少しでもできたことや頑張ったことを見つけて、ポジティブなフィードバックをすることがとても大切です。たとえば、「今日の計算、前より早くできたね」「漢字の書き順、きれいになったね」と、具体的に褒めてあげましょう。
ポジティブな言葉は、子どもに「認められている」という安心感を与え、次のやる気につながります。逆に、できなかったことばかり指摘すると、子どもはどんどん自信をなくしてしまいます。小さな成長を見逃さずに、その都度褒めてあげることで、勉強に前向きな気持ちが育っていきます。
一緒に勉強を楽しむ方法
親が一緒に勉強を楽しむことで、子どもは勉強が「つまらないもの」から「楽しい時間」へと変わります。たとえば、一緒にクイズを作って問題を出し合ったり、覚えたことを発表してもらったりするのもおすすめです。
また、勉強が終わったら一緒にごほうびのおやつを食べたり、好きな遊びをしたりすることで、「勉強=楽しいこと」と思えるようになります。親子でコミュニケーションをとりながら、楽しく学ぶ工夫をしてみましょう。
親が楽しそうに勉強に関わることで、子どもも自然と前向きな気持ちになれます。
子どもの「できた!」を見逃さない
子どもが「できた!」と感じる瞬間を見逃さずにしっかり褒めてあげましょう。
たとえば、難しい問題が解けたときや、毎日続けていた勉強が1週間続いたときなど、小さな達成感を共有することが大切です。「がんばったね」「すごいね」と一言かけるだけで、子どもの自信はどんどん大きくなります。
特に勉強が苦手な子どもにとっては、こうした成功体験が次のステップへの大きな原動力になります。親がしっかり見守りながら、一緒に成長を喜び合いましょう。
親も一緒に成長する姿勢
子どもだけに頑張らせるのではなく、親も一緒に成長する姿勢を見せることが大切です。
たとえば、親が新しいことに挑戦したり、失敗してもあきらめずに頑張る姿を見せることで、子どもは「自分もチャレンジしていいんだ」と思えるようになります。親が学ぶ姿勢を持つことで、家庭全体が「学びを楽しむ場所」になります。
失敗しても前向きに取り組む大人の姿は、子どもにとって最高のお手本です。家族みんなで一緒に成長することで、勉強嫌いの克服にもつながります。
まとめ
小学生が勉強嫌いを克服するためには、「楽しい!」と感じる瞬間をたくさん作ることが大切です。無理をせず小さな成功体験を積み重ねたり、ゲームや実験を取り入れて楽しく学んだりすることで、自然とやる気が生まれてきます。
また、勉強習慣を作るには、無理のないスケジュールや環境を整え、親子で一緒に取り組む工夫も大切です。子どもの努力や成長をしっかり見守り、ポジティブな声かけで応援してあげましょう。
親も一緒に成長する姿を見せることで、家族みんなで「学ぶ楽しさ」を実感できるはずです。今日からできる小さな工夫を続けて、勉強嫌いを一緒に乗り越えていきましょう!