春の暖かさが心地よい季節。
でもなぜか、4月を乗り切ったはずなのに気分がどんより、朝起きるのもつらくて「なんとなくやる気が出ない」……そんな経験はありませんか?
それ、もしかすると「5月病」のサインかもしれません。
新年度のスタートで張り詰めていた気持ちが、5月に入りふと緩んだ瞬間に訪れる心と体の不調。今回はそんな「5月病」について、由来や症状から、放置するリスク、そしてすぐにできるセルフケアや予防法まで、わかりやすく解説します。
「ちょっと疲れたかも」と感じているあなたへ。この記事が、少しでも心を軽くするヒントになりますように。
5月病って何?その由来を知ろう
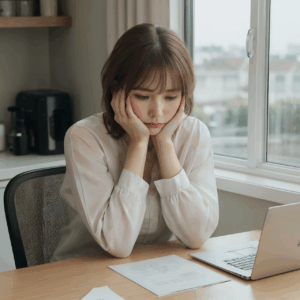
「5月病」という言葉はいつから使われているの?
「5月病」という言葉は、実は医学的な正式名称ではありません。
1970年代ごろから一般的に使われ始めた日本特有の言い回しで、新年度が始まり環境が変わる4月を過ぎたころに、心や体の不調が出ることを指して「5月病」と呼ばれるようになりました。特に新入社員や新入生に多く見られることから、メディアなどでも取り上げられるようになり、今では春の季節病のように定着しています。
この言葉の背景には、日本の社会構造や季節感が関係しています。4月にスタートする学校や会社の新年度、そこからくる期待や緊張、環境変化の連続。そしてゴールデンウィークという大型連休で気が抜けるタイミングが重なって、不調が表面化するのが5月というわけです。
つまり「5月病」とは、適応に苦しむ心の状態を指した日本独自の俗称であり、社会的なストレス反応の一種と言えます。
なぜ5月に心の不調が出やすいの?
5月に心の不調が出やすい理由は、「環境の変化と心のズレ」にあります。
4月は、新しい学校、新しい職場、新しい人間関係など、慣れないことの連続です。多くの人は緊張感と「がんばろう」という気持ちで乗り切りますが、その反動が出やすいのが5月なのです。
特に、ゴールデンウィーク後のタイミングは要注意です。長い連休でリズムが崩れたり、ふと自分の現状を振り返ったりしたとき、「このままで大丈夫かな?」「なんか疲れたな…」という思いが心に湧いてきます。このような気持ちの変化が、心の不調につながるのです。
また、季節の変わり目である春は、日照時間や気温の変化も大きく、自律神経が乱れやすい時期でもあります。こうした身体的要因も、5月に不調が出やすい理由のひとつです。
新生活とストレスの関係
新生活では、知らない人との関係構築や、新しいルールの把握、仕事内容の習得など、あらゆることに対応する必要があります。これが「適応ストレス」と呼ばれるもので、知らず知らずのうちに心と体に大きな負担をかけています。
特に完璧主義な人や真面目な人ほど、「うまくやらなきゃ」「期待に応えなきゃ」と自分を追い込んでしまう傾向が強く、ストレスが蓄積しやすくなります。これに気づかず無理をしてしまうと、5月にそのツケが回ってくるのです。
また、リモートワークやオンライン授業の普及により、孤独感や人とのつながりの薄さが不安を助長する場合もあります。ストレスとどう付き合うかが、新生活成功の鍵となります。
海外にも似たような現象はあるの?
実は、5月病に似た現象は海外にもあります。
たとえばアメリカでは「Spring Blues(春の憂うつ)」という言葉があり、季節の変わり目に気分が落ち込む人が増えることが知られています。また、北欧などでは「季節性感情障害(SAD:Seasonal Affective Disorder)」と呼ばれる、日照時間の変化による気分障害も認知されています。
ただし、日本の「5月病」は特に「新生活の疲れ」が原因として強調されており、新年度の始まりが4月という独特な制度の影響を受けている点で、やや特殊です。つまり、文化的・社会的な背景が大きく影響しているため、日本特有のストレス反応と言えるかもしれません。
5月病と正式な診断名の違いとは?
「5月病」はあくまで俗称であり、病院で「あなたは5月病です」と診断されることはありません。実際には、症状によって「適応障害」や「うつ病」などと診断されることが多いです。
適応障害は、特定のストレス要因によって一時的に心のバランスが崩れる状態。一方、うつ病は原因が特定できないことも多く、長期的かつ重度な気分の落ち込みが特徴です。5月病が放置されると、こうした本格的な精神疾患へと移行してしまうケースもあります。
つまり「5月病」は、自分自身が不調に気づくためのサインであり、早期に対処するためのきっかけとなる言葉として捉えるとよいでしょう。
こんな症状に要注意!5月病のサインとは
朝起きられない・学校や会社に行きたくない
5月病の代表的なサインのひとつが「朝、布団から出たくない」「仕事や学校に行きたくない」という気持ちです。これは単なる「怠け」や「甘え」ではありません。心がストレスに耐えきれず、脳が「もうこれ以上頑張れないよ」とサインを出している状態です。
特に朝の時間帯は、自律神経が一番乱れやすく、ストレスの影響が顕著に出やすい時間でもあります。いつもより寝坊が増えたり、準備に時間がかかってしまうなど、行動の遅れが目立ち始めたら要注意です。
また、「学校や会社に行かなきゃいけないのに、なんでこんなに気が重いんだろう」と感じる人は、すでに心が疲れ始めているサインかもしれません。このような感情は早めに認識し、自分を責めずに少し立ち止まる勇気が必要です。
イライラ・不安・気分の落ち込みが続く
感情の波が大きくなるのも、5月病の特徴です。
ちょっとしたことでイライラしたり、急に悲しくなったりすることはありませんか?
それは心がバランスを失いかけているサインかもしれません。
また、理由もなく不安が押し寄せてきたり、「何をしても楽しくない」「やる気が出ない」といった無気力感が続く場合も、5月病の可能性があります。これは脳内のセロトニンなどの神経伝達物質が乱れているために起こることが多く、放っておくと悪化する恐れがあります。
このような感情の起伏を「自分が弱いから」と思わず、「今、自分は頑張りすぎてるんだな」と優しく受け止めることが大切です。誰にでも起こり得る、自然な心の反応なのです。
集中力が続かない・物事が手につかない
「本を読んでも頭に入ってこない」「仕事や勉強に集中できない」「何をするにもやる気が出ない」——これらも5月病のよくあるサインです。脳がストレスによって疲弊していると、注意力や集中力が著しく低下します。
たとえば、会議の内容が頭に入らなかったり、授業を聞いてもぼーっとしてしまうなど、日常生活にも支障が出てきます。さらに、これが続くと自己肯定感が下がり、「自分はダメなんだ」と落ち込む悪循環に陥ってしまいます。
このような状態のときは、無理にがんばるのではなく、意識的に「何もしない時間」を作ることが回復の第一歩です。脳にも「休憩」が必要だということを、しっかり理解しておきましょう。
食欲がない・眠れないなどの体調変化

心の不調は、やがて体にも影響を及ぼします。5月病では、食欲不振や胃の不快感、過食、便秘や下痢などの胃腸トラブルがよく見られます。これはストレスが自律神経を乱すことで起こる典型的な症状です。
また、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった「睡眠の質の低下」も起きやすくなります。逆に、寝ても寝ても眠いという「過眠」の状態になることもあります。
こうした身体の変化は、心がSOSを出している証拠です。市販薬で一時的に症状を抑えるのではなく、根本的な原因(=ストレス)に目を向けることが大切です。
他の病気との違いと見分け方
5月病と似た症状を持つ病気はいくつかあります。
たとえば
「うつ病」「適応障害」「自律神経失調症」などがそうです。それらと5月病の違いは、「原因があるかどうか」「どれくらいの期間続いているか」がポイントになります。
5月病の場合は、4月からの新生活やゴールデンウィーク明けなど、比較的はっきりした「きっかけ」があり、数週間〜1ヶ月程度で回復するケースが多いです。一方で、うつ病などの場合は原因が分かりにくかったり、数ヶ月以上にわたって症状が続くこともあります。
症状が長引いたり、日常生活に大きな支障をきたしている場合は、自己判断せずに医療機関に相談することが大切です。早めの対応が、心の健康を守る第一歩です。
放っておくと危険?5月病の放置リスク
長引くと「うつ病」になる可能性も

5月病は一時的な心の疲れだと思って放置してしまう人も多いですが、それが長引くと「うつ病」などの深刻な精神疾患に進行する恐れがあります。初期の段階では「ちょっと疲れてるだけ」「連休ボケかな」と軽く考えてしまいがちですが、実はこの段階でのケアがとても重要です。
うつ病になると、気分の落ち込みが数週間〜数ヶ月続き、興味や喜びを感じる力も著しく低下します。さらに、自己否定が強くなったり、「消えてしまいたい」などの思考が生まれることもあり、放置は命に関わるリスクを伴います。
つまり、5月病は「軽いうつ状態」であることが多く、そのまま無理を重ねると心の限界を超えてしまう可能性があるのです。違和感を感じたら、早めに休む・話す・頼るというアクションが重要です。
人間関係や仕事に悪影響が出る理由
5月病の症状を抱えたまま日常生活を送っていると、知らないうちに人間関係や仕事・学業に悪影響が出てしまいます。たとえば、ちょっとしたことでイライラしてしまったり、集中力が続かずミスが増えたり、約束を忘れたりすることがあります。
これらはすべて心が疲れているサインなのですが、周囲には「やる気がない」「態度が悪い」と誤解されることもあります。そうなると職場や学校での評価が下がったり、孤立を深める結果になりかねません。
また、自分でも「なんでこんなにできないんだろう」と自己嫌悪に陥り、ますます症状が悪化するという悪循環に入ってしまいます。心と社会との間にズレが生じてしまうことで、人との関係がギクシャクしてしまうのです。
自己判断での対処が招く落とし穴
「ちょっと気分が沈んでるだけ」「寝たら治るだろう」と、自己判断で終わらせてしまうのも5月病の落とし穴です。一時的に回復したように見えても、根本的な原因を解消しなければ再発する可能性が非常に高いです。
特に「がんばり屋」タイプの人は、自分の不調に気づいても「これくらい我慢しなきゃ」と無理を重ねてしまいがちです。しかし、それが続くとある日突然、心がぽっきり折れてしまう「バーンアウト(燃え尽き症候群)」になることもあります。
また、自己流で栄養ドリンクやサプリメントに頼るのも、根本的な解決にはなりません。一時的に元気になったように感じても、精神的な疲れを隠してしまうだけで、本質的な回復にはつながらないのです。
どのくらい続くと要注意?
一般的に、5月病のような一時的な心の疲れは、2週間〜1ヶ月程度で自然と改善していくことが多いです。しかし、症状がそれ以上続いたり、日常生活に支障をきたすようになってきたら、それは「要注意」のサインです。
たとえば、「寝ても疲れが取れない」「朝がずっとつらい」「楽しみを感じない日が続いている」といった状態が2週間以上続いている場合は、専門機関に相談するべきです。また、仕事に行けない、学校に通えない、家から出られないといった行動面での支障が出てきたときも、速やかに対応が必要です。
症状が軽いうちであれば、カウンセリングや生活改善で元気を取り戻すことも可能です。無理せず、早めに「おかしいな」と感じる気持ちに素直になりましょう。
今すぐできる!5月病セルフケアのコツ
生活リズムを整えるだけで変わる
5月病のセルフケアでまず一番に意識したいのが「生活リズムの安定」です。特にゴールデンウィーク明けなどは、夜更かしや昼夜逆転などで体内時計が乱れがちです。このリズムの乱れが、自律神経のバランスを崩し、気分の落ち込みや倦怠感を強める原因になります。
生活リズムを整えるには、まず「起きる時間」を固定することが大切です。寝る時間よりも、朝の時間を一定にすることで体内時計はリセットされます。最初は少し辛いかもしれませんが、毎朝同じ時間にカーテンを開けて朝日を浴びるだけでも、脳が「朝だ!」と判断して活動モードになります。
食事の時間もなるべく毎日同じにすることで、心身が落ち着きます。朝食を抜くとエネルギー不足になりがちなので、パン1枚やバナナ1本でも良いので、何かしら食べる習慣をつけましょう。
栄養バランスを見直そう
食事は心の健康にも大きく関係しています。
特にストレスが溜まっているときは、甘いものやジャンクフードに手が伸びやすくなりますが、これがかえって心の不調を悪化させてしまう原因になることもあります。
セロトニン(幸せホルモン)を作るためには「トリプトファン」というアミノ酸が必要で、これは大豆製品・チーズ・バナナ・卵などに多く含まれています。また、ビタミンB群やマグネシウムも精神の安定に役立つので、緑黄色野菜や魚介類を積極的に取り入れるのが理想です。
逆に、カフェインやアルコール、スナック菓子などは一時的に気分が高揚しても、後で反動が来ることがあります。これらを控えるだけでも、気持ちの安定に一歩近づくはずです。
栄養は心の土台。偏らず、少しずつでも「バランスよく」がポイントです。
軽い運動・ストレッチで心と体を整える
運動は、心のリフレッシュにとても効果的です。といっても、本格的なトレーニングをする必要はありません。朝の10分間ウォーキングや、ストレッチ、ラジオ体操など、ちょっと体を動かすだけでOKです。

運動すると、脳内でエンドルフィンやドーパミンといった「気持ちを前向きにするホルモン」が分泌され、自然と心が軽くなっていきます。特に屋外での運動は、太陽の光を浴びることでセロトニンの分泌も促進されるので一石二鳥です。
もし外に出る気力がない時は、YouTubeなどでストレッチ動画を観ながら室内で体を伸ばすだけでも効果はあります。運動のポイントは「毎日少しずつ、続けること」。頑張りすぎず、できる範囲で習慣化していきましょう。
気持ちを言葉にするだけで楽になる
5月病で落ち込んでいるときは、心の中にモヤモヤが溜まりがちです。そんなときは、無理に前向きになる必要はありません。まずは、その気持ちを「言葉にする」だけでも心が軽くなることがあります。
たとえば、日記に書き出す、スマホのメモに残す、信頼できる友達や家族に「ちょっと聞いてくれる?」と話すだけでも効果があります。言葉にすることで、自分でも気づいていなかった本当の感情や原因が見えてくることがあります。
大切なのは、否定せずに「そう感じてるんだね」と自分の気持ちを受け止めてあげること。「こんなことで悩むなんて…」と比較する必要はありません。あなたの感じていることは、あなただけの大事な感情です。
スマホとの付き合い方もポイント
スマホの使いすぎも、5月病を悪化させる原因のひとつです。
特にSNSを見ていると、他人の「楽しそうな投稿」に心がざわついてしまうことがあります。これは無意識のうちに「自分はうまくいってないのに」と比較してしまうからです。
また、寝る前にスマホを使うと、ブルーライトの影響で睡眠の質が下がり、翌朝にだるさや集中力の低下を招きます。心のリズムも狂ってしまうため、「スマホとの距離感」を見直すこともセルフケアの一環です。
具体的には、SNSの使用時間を決める、寝る1時間前にはスマホを見ない、スマホは寝室に持ち込まないなど、少しずつルールを設けていくと良いでしょう。情報の波から少し離れるだけでも、心が落ち着きやすくなります。
無理しない環境づくりで5月病を予防しよう
「がんばりすぎない」がキーワード
5月病を予防するうえで一番大切なのは、「がんばりすぎないこと」です。日本の文化では「努力」や「我慢」が美徳とされることが多く、つい自分の限界を超えてまで頑張ってしまう人が少なくありません。しかし、その無理が心身のバランスを崩し、5月病の原因になってしまうのです。
特に新年度や新生活が始まると、「完璧にこなしたい」「周りに迷惑をかけたくない」と気合が入りがちですが、最初から100点を目指さなくても大丈夫です。失敗しても、「まあいっか」と自分を許すことができれば、心の余裕が生まれます。
「今日は60点でOK」「がんばらない日もあっていい」という考え方を持つことで、気持ちが楽になります。無理に背伸びせず、自分のペースを大切にしましょう。
周囲のサポートを活用しよう
5月病を予防・改善するためには、「ひとりで抱え込まない」ことが大切です。特に日本人は「迷惑をかけたくない」「弱音を吐くのは恥ずかしい」と思いがちですが、周囲に頼ることは決して悪いことではありません。
同僚や先輩、友人、家族など、話せる人に気持ちを打ち明けることで、気持ちが楽になることがあります。「こんなことで相談していいのかな?」と思わず、「最近ちょっとしんどくてさ」と自然に話してみましょう。意外と同じように感じている人がいて、共感し合えることもあります。
また、学校や職場には保健室やカウンセラー、産業医など専門のサポートもあります。「困ったら相談できる場所がある」と知っておくだけでも、安心感につながります。
休む勇気を持つことの大切さ
5月病を防ぐためには、思い切って「休む」ことも大切です。
心や体に不調を感じたら、無理に行動を続けるよりも、しっかりと休養をとったほうが回復は早まります。
しかし多くの人は「ここで休んだら置いていかれるんじゃないか」「甘えていると思われたくない」と不安になりがちです。でも、長く走るためには、途中で一息つくことも必要なのです。
実際、会社でも「メンタルヘルス休暇」や「有給休暇の取得推奨日」を設けているところも増えてきています。1日でも休んで心をリセットできれば、その後のパフォーマンスがぐっと上がることもあります。
「心のガソリン切れ」になる前に、休む勇気を持ちましょう。疲れたら、立ち止まっていいのです。
自分に合ったリラックス法を見つける
リラックスの方法は人それぞれです。
音楽を聴く、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、アロマの香りを楽しむ、自然の中を散歩する、趣味に没頭するなど、自分が「ホッとできる瞬間」を意識的に作ることが大切です。

大事なのは、「こうしなきゃ」という決まりに縛られないこと。「寝っ転がってボーッとする」「好きなアイスを食べる」など、どんな小さなことでも、自分がリラックスできるならそれでOKです。
おすすめは、自分の「快適リスト」を作っておくこと。「落ち込んだときはこの音楽」「疲れた日はこの入浴剤」など、あらかじめ用意しておくことで、ストレスを感じたときにすぐ対処できます。
日々の中に、少しでも「自分をいたわる時間」を組み込んでみてください。
学校や職場でできる予防策とは
学校や職場でも、ちょっとした工夫で5月病を予防することができます。たとえば、スケジュールを詰め込みすぎないことや、こまめに休憩をとること、できるだけ人との会話を増やすことがポイントです。
また、新人や後輩がいれば、声をかけたり相談に乗ってあげることで、自分自身の心も安定します。お互いに支え合える環境を作ることで、「ひとりじゃない」という安心感が生まれます。
職場であれば、上司に対して業務量の相談をすることも大切です。我慢しているだけでは状況は変わりません。適切なコミュニケーションが、心の健康を守るカギになります。
学校でも「保健室登校」や「スクールカウンセラー利用」など柔軟な対応ができる場合があります。制度やサポート体制を事前に把握しておくことで、いざという時にすぐ行動できるようになります。
まとめ

5月病は、多くの人が春の環境の変化に適応しきれずに感じる一時的な心と体の不調です。日本の新年度という特有のライフサイクルが背景にあり、「なんとなくやる気が出ない」「朝がつらい」といった症状が表れます。
しかし、この状態を「ただの怠け」や「気のせい」で済ませてしまうと、うつ病など深刻な状態に進行してしまうリスクもあります。大切なのは、自分の変化に気づき、無理をせず、早めにセルフケアや周囲のサポートを取り入れることです。
生活リズムの見直し、食事や運動などの習慣の改善、そして気持ちを言葉にすることが、心の安定に大きくつながります。また、予防として「がんばりすぎない環境づくり」も非常に重要です。
心が疲れたと感じたら、自分を責めずに一度立ち止まってみてください。あなたの心は、あなた自身がいちばん大切にしてあげるべき存在です。


