夜になると急に気になる冷蔵庫の音。
「昼間は静かだったのに、なぜか夜だけうるさい…」そんな経験はありませんか?実はこれ、冷蔵庫の不具合とは限らず、環境や音の感じ方に原因があるかもしれません。
この記事では、冷蔵庫の音が夜だけ気になる理由と、その対策をわかりやすく解説します。今すぐできる防音対策から、買い替え時に注目すべきポイントまで、中学生でも理解できるように丁寧にご紹介。
睡眠を邪魔される夜の騒音問題を解決したい方は、ぜひ最後までお読みください!
冷蔵庫が夜だけうるさいのはなぜ?その原因を徹底解説

静かな夜だから気になる?人間の聴覚の仕組み
夜になると冷蔵庫の音が気になる理由のひとつは、「周囲の静けさ」にあります。人間の耳は、周囲の音が静かになればなるほど、微細な音に敏感になります。日中はテレビの音や人の話し声、外の騒音などで冷蔵庫の動作音はあまり気になりませんが、夜間はこれらの音がほとんどなくなるため、冷蔵庫の音だけが目立ってしまうのです。
特に、睡眠前や就寝中は脳もリラックスしているため、ちょっとした異音でも「不快」と感じやすくなります。また、静かな環境下では通常気づかないような小さな「カタカタ音」や「ブーンという音」などが耳につくことがあります。これは冷蔵庫に限らず、エアコンや加湿器などの家電にも言えることですが、冷蔵庫は24時間稼働しているため特に顕著です。
つまり、冷蔵庫の音が「夜だけ大きくなる」わけではなく、「夜になると他の音が減るため相対的に大きく感じる」という心理的な要因が大きいのです。この点を理解するだけでも、音に対する不快感が少し和らぐかもしれません。
コンプレッサーの仕組みと稼働タイミング
冷蔵庫の中核を担うコンプレッサーは、庫内の温度を一定に保つために断続的に動いています。このコンプレッサーはモーターの一種であり、作動時に「ブーン」「ウィーン」といった低い音を発生させます。特に夜間は気温が下がることで庫内温度との差が大きくなり、センサーが温度調整を頻繁に行うようになることがあります。
たとえば、冷蔵庫のドアを頻繁に開閉したり、温かい食べ物を入れたりした直後は、コンプレッサーが一気に稼働して温度を下げようとします。このタイミングが夜間に重なると、急激な動作音が発生し、それが睡眠中に気になるというケースもあります。
また、最近の省エネ冷蔵庫は「インバーター制御」がされていて、必要な分だけ動作するようになっていますが、それでも古い機種や安価なモデルでは一定時間ごとにフルパワーでコンプレッサーが動くことがあります。このような機種では、夜間に集中して音が大きくなる印象を持つことがあります。
温度センサーと夜間の室温変化の関係
夜になると部屋の温度が下がるのは自然なことですが、これが冷蔵庫の動作にも影響するのをご存知ですか?冷蔵庫には内部と外部の温度を感知するセンサーが搭載されており、周囲の室温が下がると、冷却の頻度や強さを調整するようになっています。
特に古い冷蔵庫やセンサーの精度が低い機種では、室温が急激に変化するとそれに過敏に反応してしまい、必要以上に冷却しようとします。これにより、コンプレッサーやファンが頻繁に作動し、夜間に音が大きく感じられるのです。
また、冷蔵庫が直射日光を受ける場所にあったり、昼間に熱がこもりやすい環境にあると、夜になって温度差が大きくなり、その差を補おうとして急に冷却を始めることがあります。夜中に「ゴォーッ」という音がしたり、断続的に「ウィーン」と唸るような音が聞こえる場合は、こうしたセンサーの働きが関係している可能性があります。
冷蔵庫の設置場所が影響しているかも?
冷蔵庫の設置場所も、夜間の音の感じ方に大きく影響します。特に、床がフローリングやタイルの場合、冷蔵庫から発せられる振動音が床を伝って室内に響くことがあります。夜は建物全体が静かになるため、この微細な振動音がよく聞こえるようになります。
また、冷蔵庫の背面や側面に十分なスペースがない場合、排熱がうまくいかず、冷却機能が過剰に働いてしまうことも。その結果、ファンやモーターが通常より大きな音を出す可能性があります。特に壁にピッタリとくっつけて設置していると、壁を通じて振動が共鳴し、思っている以上に「うるさく」感じることもあります。
さらに、床が水平でないと冷蔵庫の脚がうまく接地できず、本体がわずかにガタつくことも。これにより、冷蔵庫の動作時に「カタカタ」と小さな揺れ音が発生し、それが夜になると耳障りに感じられる場合もあるのです。
実は劣化のサインかもしれない重要チェックポイント
冷蔵庫が夜だけうるさいと感じていても、実はそれが「故障の前兆」である可能性も否定できません。とくに、以下のような音がする場合は要注意です。
-
異常な金属音(「カンカン」「キーン」など)
-
動作中に急に音が止まる・再開する
-
ファンが回っていないような無音状態が長く続く
-
異常に長くコンプレッサーが動き続ける
これらの症状は、ファンモーターの劣化、コンプレッサーの寿命、センサー異常などが考えられます。初期の段階では夜間にのみ気になる程度の症状かもしれませんが、放置すると完全に冷却できなくなったり、電気代が急に高くなることも。
音が気になるようになった時点で、一度メーカーのサイトや取扱説明書を確認し、「正常な動作音」との違いを把握しておくと安心です。また、使用年数が10年を超えている場合は、そろそろ買い替えも視野に入れて検討することをおすすめします。
すぐできる!冷蔵庫の騒音を減らすための工夫

設置場所を見直すだけで静かになる?
冷蔵庫の音が気になるとき、まず見直すべきなのが「設置場所」です。実は、冷蔵庫の置き方や周囲の環境によって、音の伝わり方が大きく変わるのです。特にフローリングや木材の床では、冷蔵庫の振動音が床に伝わりやすく、夜間の静けさの中で「ブーン」という音が響いてしまうことがあります。
また、壁にピッタリと設置している場合、排熱がうまく逃げず、冷却機能が過剰に働くことで音が大きくなる原因に。理想は、背面と左右に5cm以上、上部には10cm以上の隙間を確保すること。これにより排熱がスムーズになり、冷蔵庫の稼働音も安定します。
さらに、冷蔵庫の脚がしっかりと床に接地しているかも重要です。床がわずかに傾いているだけで、冷蔵庫がガタついて音が発生することがあります。付属のアジャスターで水平を調整することで、音の軽減につながることが多いです。
わざわざ専門の業者に頼まなくても、設置場所の確認と微調整だけで静音効果が期待できますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
冷蔵庫の下に防振マットを敷いてみよう
冷蔵庫の下に「防振マット」や「防音シート」を敷くのも効果的な対策のひとつです。冷蔵庫の振動は床を通じて増幅されることがあるため、その伝わり方を吸収・軽減するマットを使えば、音の広がりを抑えることができます。
市販の防振マットはホームセンターやネット通販で簡単に手に入り、価格も1,000円〜2,000円程度とお手頃。設置も難しくなく、冷蔵庫の脚の下に差し込むだけでOKです。中には防振と同時に床の傷防止にもなるものもあります。
選ぶときは「耐荷重」がポイント。冷蔵庫の重さに耐えられるマットを選ばないと、つぶれて効果がなくなりますので、必ず製品の仕様を確認しましょう。また、素材としては「ウレタンゴム」や「EVA素材」などが吸音・耐久性ともにおすすめです。
冷蔵庫が床に接している部分にこうしたマットを挟むことで、振動が抑えられ、夜間の「ブーン」や「ジリジリ」といった音がかなり軽減されることがあります。手軽で効果的な方法なので、まず試してみる価値ありです。
ドアの開け閉めにも要注意!気密性の影響
意外と見落としがちなのが、冷蔵庫のドアの開閉による影響です。ドアの開け閉めが頻繁だったり、しっかり閉まっていなかったりすると、庫内の温度が上がり、冷却装置がフル稼働してしまいます。その結果、コンプレッサーが長く動作し、大きな音が出る原因になります。
特に夜に夕食の片付けをした後、温かい料理をそのまま冷蔵庫に入れてしまうと、庫内の温度が一気に上昇し、コンプレッサーが強めに稼働し始めます。すると、寝る時間とちょうど重なって、「ゴーッ」とした音が響き渡ることも。
また、ドアパッキンが劣化していると、しっかり閉まっているように見えても隙間から冷気が漏れてしまい、温度調整がうまくいかなくなります。これも稼働音を大きくする要因です。
定期的にパッキンの汚れや変形をチェックし、必要に応じて交換することも大切です。ドアを開ける時間を短くする、開ける回数を減らすなど、ちょっとした心がけで冷蔵庫の音を静かに保つことができます。
詰めすぎNG?庫内の物の入れ方も関係
冷蔵庫の中にものを詰め込みすぎると、空気の流れが悪くなり、温度センサーがうまく働かなくなることがあります。その結果、冷却装置が必要以上に稼働してしまい、音が大きくなる原因になります。特にファン付きのモデルでは、庫内にあるファンが詰まった食品に干渉して「カタカタ」「ガリガリ」と異音を出すことも。
また、冷気は庫内の上から下に流れるため、ぎっしり詰まった状態では冷気が行き渡らず、一部のエリアが冷えにくくなります。これもセンサーが異常を感じ取り、より強力に冷却しようとする原因となります。
理想は、冷蔵室内の70%程度の収納率を保つこと。これなら冷気が循環しやすく、ファンもスムーズに動作します。また、食品の配置にも工夫を加えましょう。風の通り道を確保し、背の高いものは後ろ、低いものは前に置くと冷却効率がアップします。
さらに、食品を入れる際にラップやタッパーでしっかり密閉することも大切です。開放状態の食品があると湿気が庫内に広がり、これも冷却効率を下げてしまいます。ちょっとした工夫が音の軽減に大きくつながります。
音の種類で対処法を変えるのがコツ
冷蔵庫の音にも種類があり、それぞれ原因や対処法が異なります。まず、よくある「ブーン」という低音はコンプレッサーが稼働しているときの音で、ある程度は仕方のないものです。ただし、この音が以前より長くなったり大きくなった場合は要注意です。
「カタカタ」「コトコト」という音は、冷蔵庫内部の部品が振動していることが原因の場合があります。庫内のトレイがしっかりはまっていなかったり、食品が揺れてぶつかっていることもあるので、固定し直すだけで解消できることも。
「ガリガリ」「キュルキュル」といった金属的な音は、ファンに異物が当たっていたり、モーター部分が摩耗している可能性があります。この場合は内部の清掃や、部品の交換が必要になることもあります。
音の種類と発生タイミングをよく観察して、「どこから出ている音か?」を見極めることが、適切な対処の第一歩です。スマホの録音機能などを使って音の記録をとっておくと、サポートに相談する際にも役立ちます。
故障かどうかを見極めるチェックポイント
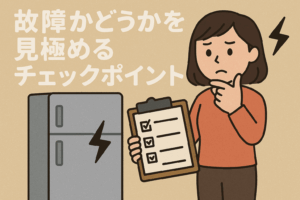
異音の種類別「正常」と「故障」の見分け方
冷蔵庫の音が気になるとき、それが「故障」なのか「正常な動作音」なのかを見極めることはとても大切です。冷蔵庫は24時間稼働する家電ですので、ある程度の音が出るのは当然です。しかし、明らかにこれまでと違う音がしたり、頻度や音量が変わった場合には注意が必要です。
たとえば、以下のような音は正常な範囲とされています:
-
「ブーン」という低い音(コンプレッサーの動作音)
-
「カチッ」という小さな音(リレーの切り替え音)
-
「ポコポコ」「チリチリ」といった音(水の流れる音や霜取り時の音)
一方、以下のような音は故障のサインの可能性があります:
-
「ガリガリ」「キュルキュル」といった金属が擦れるような音
-
「カンカン」「コンコン」といった打撃音
-
断続的に鳴る大きな振動音や異常に長い駆動音
-
突然止まり、その後再び大きな音とともに動き出す
これらの異音が継続するようであれば、内部部品の摩耗やセンサーの不具合、ファンに異物が混入しているなどの可能性があります。音を聞き分け、変化に気づくことが冷蔵庫を長持ちさせるコツです。
モーター音とファン音の違いとは?
冷蔵庫には主に2種類の「動作音」が存在します。それがモーター音とファン音です。どちらも冷却機能に関わる重要な音ですが、それぞれの音の特徴を知っておくことで、故障かどうかの判断がしやすくなります。
まず、モーター音(コンプレッサー音)は「ブーン」「ゴーッ」といった低くて持続的な音です。これは庫内の温度が上がったときに冷却のために作動するため、一定時間だけ鳴るのが普通です。これが頻繁に、あるいは長時間続くようなら、庫内がうまく冷えていない可能性があります。
次に、ファン音は「シャー」「ヒュンヒュン」といった風を切るような軽い音です。これは冷気を庫内全体に循環させるためのもので、断続的に鳴るのが普通です。しかし、ファンに氷がこびりついていたり、異物が当たっていたりすると、「ガリガリ」「カタカタ」と異音に変化することがあります。
音の高さやリズム、持続時間を意識して聞き分けてみましょう。録音して比べてみると、違いがはっきりわかることもあります。
いつから?どのくらいの音?記録が大事
冷蔵庫の異音や不具合に気づいたとき、最も大事なのは「状況の記録」です。例えば、夜中の何時ごろに音がし始めたか、どれくらいの時間続いたか、どんな音がしたかをメモしておくことで、修理業者やメーカーサポートに相談するときに非常に役立ちます。
記録するべきポイントは以下の通りです:
-
音が発生した時間帯と継続時間
-
音の種類(例:ブーン、カタカタ、ガリガリなど)
-
音の大きさ(以前より大きくなったかどうか)
-
ドアの開閉や食品を入れた直後かどうか
-
冷却性能に変化があったか(冷えが弱いなど)
これらをスマホのメモアプリや紙のメモ帳に記録するだけでOKです。また、可能であればスマホで音声を録音しておくとより正確に伝えることができます。
メーカーや修理業者は状況を詳しく伝えられるほど、診断がしやすくなり、対応もスムーズになります。面倒に感じるかもしれませんが、長い目で見ればトラブルの早期発見・解決につながります。
メーカーや型番ごとの特徴を調べよう
冷蔵庫の音には「メーカー特有のクセ」がある場合もあります。たとえば、あるメーカーでは霜取り中に「パキッ」という音が鳴る仕様があり、それが正常とされていることも。一方、別のメーカーでは同じ音が不具合扱いされることもあるのです。
そのため、まずはご自身の冷蔵庫の「型番」と「メーカー名」を確認しましょう。多くの場合、冷蔵庫の内側のドア周辺や背面にシールで記載されています。それを元に、メーカーの公式サイトや取扱説明書で仕様やQ&Aを確認すると、気になる音が「正常」か「異常」かが判断しやすくなります。
また、製造年やモデルによっても静音性能や構造に違いがあるため、ネットで「型番+異音」などで検索すると、同じ症状に悩むユーザーの情報が見つかることもあります。公式のサポート情報だけでなく、口コミやレビューも参考になるので、複数の情報源から調べてみましょう。
無理に修理せず、まずはサポートセンターに相談
音が気になったからといって、すぐに冷蔵庫を分解しようとするのは危険です。内部には高電圧部品や精密センサーが含まれており、素人が触ることで余計に悪化させてしまう可能性もあります。
もし異音が続く、明らかにこれまでと違うと感じた場合は、まずメーカーのサポートセンターに相談することをおすすめします。保証期間内であれば無料で点検・修理してもらえることもありますし、仮に保証が切れていても、症状の相談だけなら無料で受け付けてくれるところも多いです。
相談時には、「型番」「使用年数」「異音の種類」「発生時間帯」など、先ほど記録した情報をもとに話すとスムーズです。最近ではLINEやチャットでもサポートを受けられるメーカーも増えており、手軽に相談できる環境が整ってきています。
自己判断で分解するよりも、プロに相談して適切な対応をしてもらう方が、安全で確実です。
夜の静けさを守るためにできる生活の工夫

タイマー付き家電で「音の分散」を
夜になると冷蔵庫の音が気になって眠れない…という方は、音の分散という考え方を取り入れてみましょう。これは、「冷蔵庫だけが音を出している状態を避ける」ために、あえて他の生活音を適度に混ぜて耳を慣れさせる方法です。
たとえば、加湿器や空気清浄機などの家電をタイマーで夜間に動作させることで、一定の低い環境音が生まれ、冷蔵庫の音が目立ちにくくなります。これを「ホワイトノイズ効果」とも呼びます。人間の耳は、まったく無音の状態よりも、適度に音がある環境のほうが不規則な音に対して敏感になりにくくなるのです。
さらに、スマートコンセントを活用すれば、家電のオン・オフをアプリで時間指定でき、音を意図的に分散させることができます。「寝る1時間前に空気清浄機をON」「寝た後2時間で自動停止」など、カスタマイズも簡単です。
冷蔵庫の音を完全に消すことはできませんが、こうした“音の環境づくり”で精神的なストレスを軽減することができます。
寝室との距離を取るレイアウトの工夫
冷蔵庫の音が夜に気になる大きな理由は、「距離が近すぎる」ことです。ワンルームや1Kの間取りの場合、キッチンと寝室が同じ空間にあることも多く、冷蔵庫の音が直に耳に入ってきます。
このような場合、まず考えたいのが冷蔵庫と寝具の距離をできるだけ離すこと。1〜2メートル離れるだけでも音の感じ方は大きく変わります。可能であれば、冷蔵庫を壁際に寄せ、ベッドを反対側の角に配置すると効果的です。
また、冷蔵庫と寝室の間に収納棚やカーテンを置くだけでも音の伝わり方が抑えられます。背の高い本棚やパーティションを使って空間を区切れば、音だけでなく視覚的にも冷蔵庫の存在を遠ざけることができます。
壁を動かせない限り完璧な遮音は難しいですが、レイアウトを工夫することで「音の直撃」を避けることができます。特に引っ越し直後などには、冷蔵庫の位置を優先して家具配置を考えるのがポイントです。
防音カーテンやパーティションの活用法
音の通り道を遮るには、防音アイテムの活用も非常に効果的です。冷蔵庫の音が響いて困っているなら、防音カーテンや吸音パネルを使って「音を遮る壁」を作ってみましょう。
たとえば、冷蔵庫とベッドの間に防音カーテンを吊るすだけでも、音の直進を防げるのでかなり静かに感じるようになります。遮光カーテンに似た素材で、防音タイプのものも市販されています。
また、家具の裏側に取り付けられる吸音パネルもおすすめです。フォーム状のパネルやフェルト素材の吸音材を、冷蔵庫の背面や壁に貼ることで、反響音を抑えることができます。これにより、「耳に残る感じ」の音が軽減されます。
最近では、Amazonなどでもデザイン性の高い防音インテリアが手軽に手に入るため、インテリアの雰囲気を損なわずに対策できるのも魅力。完全な防音は難しくても、「少しでもマシ」にする工夫はたくさんあります。
ホワイトノイズで冷蔵庫音をカバーする方法
前述の通り、冷蔵庫の音は「他の音がないから気になる」ことが多いです。そこで、就寝中にホワイトノイズを流すことで、冷蔵庫の音を心理的にカバーする方法があります。
ホワイトノイズとは、一定の周波数で雑音のように聞こえる音で、自然界でいえば「波の音」「風の音」「雨の音」などがそれにあたります。この音を耳に流しておくと、冷蔵庫の「不規則な音」が脳に届きにくくなり、結果的に眠りやすくなるのです。
スマートフォンの無料アプリやYouTubeでも、ホワイトノイズを流せるサービスがたくさんあります。「white noise sleep」などで検索すると、自然音系や電子音系のさまざまなバリエーションが見つかります。
Bluetoothスピーカーなどを使って低音で流しておけば、気になっていた冷蔵庫の音もだいぶ緩和されます。音に敏感な方ほど試してみる価値がある方法です。
見落としがちな床や壁の音の反響にも注意
実は、冷蔵庫の音自体が大きいのではなく、「部屋の構造によって響いている」だけの場合もあります。特に床がフローリング、壁がコンクリートやタイルなど硬い素材の場合、音が反射しやすく、実際の音以上に大きく聞こえるのです。
このような環境では、音が跳ね返る方向に吸音材を置くのが効果的。たとえば、壁に絵やファブリックパネルを飾る、床にラグやカーペットを敷くなど、素材で音を吸収する工夫をしてみましょう。
また、部屋の角は音が溜まりやすい「反響ポイント」なので、角に観葉植物やクッションなどの柔らかい物を置くだけでも音の印象が変わります。まるでカフェのような“こもり感”が生まれ、冷蔵庫の音がやわらかく感じられるようになります。
ちょっとした模様替えやインテリア変更でも、音環境は劇的に改善されることがあります。ぜひ、目ではなく「耳」で部屋の雰囲気を捉えてみてください。
修理か買い替えか?冷蔵庫との付き合い方

音のトラブルは修理で直る?ケース別解説
冷蔵庫から異音がする場合、「修理で直るのか、それとも買い替えるべきか」と悩む方も多いと思います。実際には、音の原因によって対応は大きく変わります。
まず、比較的軽度なケースでは、ファンに氷が付着しているだけということもあります。この場合は、冷蔵庫を一度電源オフにして中身を取り出し、1日ほど自然解凍すれば改善されることがあります(※説明書を確認してから実施を)。
また、ファンモーターの劣化やベアリングの摩耗など、部品交換だけで済む場合もあります。修理費用はおよそ5,000円〜15,000円程度が目安で、保証期間内なら無償で対応してもらえることもあります。
一方で、コンプレッサーや制御基板の故障となると修理費が20,000円以上かかることが多く、年式が古いモデルの場合は部品がもう手に入らないというケースもあります。こうなると、修理より買い替えの方が現実的です。
症状をしっかり観察して、サポートセンターに相談すれば、修理可能かどうかの見通しは割と簡単につきます。焦って判断せず、まずはプロに相談するのが最善です。
メーカー保証と延長保証を確認しよう
修理を検討する場合、必ずチェックしておきたいのが「メーカー保証」と「延長保証」です。多くの冷蔵庫には購入から1年間のメーカー保証が付いていますが、販売店独自の5年〜10年の延長保証に入っている場合もあります。
特に大手家電量販店(ヨドバシ、ビックカメラ、ヤマダ電機など)で購入した場合、延長保証が無料で付いていたり、わずかな追加料金で加入していることがあります。保証書やレシート、マイページなどで確認してみましょう。
保証内であれば、たとえ高額な修理でも無料または格安で対応してもらえるため、音のトラブルで悩んでいるならまず保証の有無を確認することが大切です。
また、保証期間が切れていても、「リコール対象」や「メーカー自主修理対象」として無料で対応してもらえるケースもあります。公式サイトやSNSで情報を検索してみると、思わぬ発見があることも。
保証の確認は面倒に感じがちですが、損をしないためにも必ずチェックするクセをつけましょう。
買い替えるならどんな冷蔵庫が静か?
いざ買い替えることになった場合、「今度は静かな冷蔵庫を選びたい」と思うのが自然です。静音性の高い冷蔵庫には、いくつかの共通した特徴があります。
まずチェックしたいのが、**「インバーター搭載モデル」**であること。インバーター制御により、必要な時にだけ適切な出力で運転するため、音が小さく抑えられます。省エネ性能も高いので、電気代の節約にもつながります。
次に、冷却方式にも注目。直冷式よりも**ファン式(間冷式)**の方が温度ムラが少なく、稼働時間も短いため音が目立ちにくい傾向があります。
さらに、「静音性〇〇dB」といった表示を見つけたら、それも参考にしましょう。一般的には、40dB以下なら図書館レベルの静かさで、寝室にも適しています。
最近では「静音モデル」として明記されている製品もあるので、口コミやレビューでの評判もチェックして、自分に合ったモデルを選ぶことが大切です。
静音性に優れた冷蔵庫の選び方
静かな冷蔵庫を選ぶ際は、以下のポイントを総合的に見ると失敗しません:
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| インバーター制御 | モーターの出力を自動調整。音が静か |
| ファン式冷却 | 温度ムラが少なく静か。手入れも楽 |
| 静音設計(dB) | 目安:40dB以下なら静かな部屋向き |
| コンパクトサイズ | 小型ほど稼働音が小さい傾向あり |
| レビュー評価 | 「夜でも静か」「音が気にならない」などの声があるか |
| メーカー実績 | パナソニック、日立、三菱などの実績をチェック |
このように、スペックと実際の使用者の声をバランスよく見ることで、「買ってから後悔しない冷蔵庫選び」ができます。できれば店舗で実物を見たり、実際の運転音を確認できるモデルなら、より安心です。
価格だけで決めない!長く快適に使うポイント
冷蔵庫を買うとき、「できるだけ安く済ませたい」と思う気持ちは当然ですが、価格だけで選んでしまうと後悔することも。特に静音性を重視するなら、多少高くても性能にこだわるべきです。
安価なモデルにはインバーターが搭載されていなかったり、ファンがうるさかったりする場合があります。しかも、消費電力が大きく電気代が高くつくことも。長く使う家電だからこそ、最初の投資で快適さが何年も続くと考えれば、費用対効果は高いのです。
また、購入時は必ず「サイズ」や「搬入経路」も確認しておきましょう。静音性を重視して買ったのに、搬入できなかったり、部屋に置けなかったりするのは本末転倒です。
長く静かに使うためには、購入時のチェック、設置環境の整備、使い方の工夫、この3つを意識することが大切です。冷蔵庫は“生活音の中心”になりうる存在だからこそ、丁寧に選びたいですね。
【まとめ】冷蔵庫の音が夜だけ気になるあなたへ
夜だけ冷蔵庫の音がうるさく感じる…。そんな悩みは、決してあなただけのものではありません。この記事では、冷蔵庫が夜間に音を発する理由から、すぐできる対策、故障との見分け方、そして買い替え時のポイントまで幅広く解説してきました。
実際には、夜間は周囲が静かになるため、冷蔵庫の通常の動作音でも耳につきやすくなります。また、設置場所や使用環境によっては、音が増幅されてしまうことも。対策としては、設置場所の見直し、防振マットの活用、ドアの閉まり具合のチェック、家具の配置の工夫などが有効です。
もし異常な音や長時間の作動が気になる場合は、早めに記録を取り、メーカーサポートに相談しましょう。修理で済むこともありますし、買い替えがベストな選択肢となる場合もあります。今後は静音性能に注目した冷蔵庫選びを意識して、快適な生活環境を手に入れてください。


