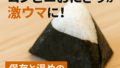「また行きたくないって言ってる…どうすればいいの?」
習い事に通っている子供が突然「行きたくない」と言い出すと、戸惑ってしまう親は
多いものです。怒ってしまう?やめさせる?それとも無理にでも行かせるべき?
この記事では、子供が習い事を嫌がるときの本当の理由や、親としてどう向き合えばいいのかをわかりやすく解説します。やめる?続ける?その判断の分かれ道、子供のやる気を引き出すコツ、そして「うちの子らしさ」を大切にした習い事との付き合い方まで、実例を交えてご紹介。
迷える親御さんに寄り添う、保存版のガイドです。
親が知っておきたい「習い事イヤ」の本当の理由
子供が言葉にできない「気持ち」の正体とは?
子供が「行きたくない」と言ったとき、その言葉の裏には、単なるワガママではなく何らかの理由や感情が隠れていることがほとんどです。ただし、その気持ちを子供自身がはっきりと言葉にできないことがよくあります。
たとえば、「つまらない」「うまくできない」「友達がいない」「先生が怖い」といったネガティブな感情があるかもしれません。でも子供はそれを「行きたくない」の一言で表現してしまうのです。
このときに大切なのは、否定や説得ではなく、まずはその気持ちを「そう思うんだね」と受け止めてあげること。子供にとって、親が自分の気持ちを理解してくれたという安心感はとても大きな支えになります。
また、毎回「行きたくない」と言っているのか、それともたまたまなのかも見極めるポイントです。一時的な疲れや気分のムラで言っている場合もありますし、習い事が苦痛になってきているサインの場合もあります。
話をじっくり聞く時間をつくって、子供の中にある気持ちを少しずつ引き出していきましょう。
大人の想像と違った理由が隠れていることも珍しくありません。
「どうして?」と問い詰めるより、「最近どう感じてる?」とやさしく聞いてみると、
心の扉が少し開くかもしれません。
年齢ごとに変わる嫌がる理由
子供の「行きたくない」には、年齢ごとに特徴的な理由があります。年齢によって
成長段階や感情の発達が異なるため、親の対応の仕方も変える必要があります。
未就学児(3~6歳)の場合、感情のコントロールがまだ未熟で、「今日は眠い」「お腹が空いてる」「テレビが見たい」など、そのときの気分が理由になっていることが多いです。この年代はスケジュールやルールに縛られるのが苦手なので、習い事も「遊び感覚」で取り入れるのがコツです。
小学校低学年(7~9歳)になると、周囲との比較や成功体験・失敗体験が影響してきます。「できない」「注意される」「友達より下手」といった劣等感から来るストレスが原因になることも。この年齢では「結果よりもがんばった過程を認める声かけ」が大切になります。
小学校高学年(10~12歳)になると、自我が強くなり、自分でやりたい・やりたくないをはっきり言うようになります。興味や価値観の変化も大きく、「最初は楽しかったけど今は違う」と思うことも出てきます。思春期の入り口として、自分の意見を尊重してもらいたい気持ちが強くなるため、頭ごなしに否定せず「選ぶ自由」を与えることが信頼関係を築くカギになります。
年齢に応じた関わり方をすることで、子供の「行きたくない」の背景を理解しやすくなります。
習い事のタイプ別に見る「やめたくなる原因」
習い事の内容によって、子供がやめたがる理由も異なります。たとえば、スポーツ系の習い事であれば「体力的にきつい」「コーチが厳しい」「勝てなくてつまらない」などが挙げられます。特に団体競技では、チーム内での人間関係もストレスになることがあります。
音楽や学習系では、「練習が苦痛」「上達しない」「他の子と比べられて落ち込む」といった精神的な理由が多くなりがちです。また、親の期待がプレッシャーになってしまうことも。
アートや表現系の習い事(絵画・ダンス・演劇など)の場合は、「自由すぎて何をすればいいのかわからない」「自己表現が恥ずかしい」などの理由で続けるのが難しくなることがあります。
このように、習い事ごとにありがちな「つまずきポイント」を知っておくと、事前に対策を立てたり、子供の気持ちをより深く理解したりすることができます。
「この習い事が合っていないのかも」と思ったら、
一度見直してみるのも選択肢のひとつです。
家庭環境との関係性はある?
意外と見落とされがちなのが、家庭環境や親の関わり方が
習い事へのモチベーションに影響を与えているケースです。
たとえば、共働きで送迎がバタバタしている家庭では、子供も「慌ただしい」「落ち着かない」と感じてしまい、習い事自体を負担に思うようになることがあります。親がイライラしていたり、焦って送り出していたりすると、子供もその空気を敏感に感じ取るのです。
また、「弟や妹にばかり構ってもらえてない」「自分だけ違う場所に連れて行かれる」など、
ちょっとした寂しさが「行きたくない」という言葉に現れる場合もあります。
家庭内での会話や、子供とのスキンシップの時間が減っている場合は、まずはそのバランスを見直してみましょう。子供が安心して習い事に向かえるような環境を整えることも、親の大事な役割です。
周囲の子との比較がプレッシャーになる?
「○○ちゃんはもう跳べたよ」「△△くんはもう両手で弾けるって」など、つい言ってしまいがちな比較の言葉。これが子供にとって大きなプレッシャーになることがあります。
子供は大人以上に、他人との違いに敏感です。特に習い事の場は、技術や成績が見えやすいため、「自分はダメなんだ」と自己肯定感が下がりやすい環境でもあります。
また、同じ教室に優秀な子が多いと、それだけで通うことにストレスを感じてしまう子もいます。親が他の子を持ち上げる言い方をすることで、無意識に「自分は比べられている」と感じてしまうこともあるのです。
大切なのは「昨日の自分と比べること」。
小さな成長や努力を認めてあげることで、
プレッシャーを乗り越える力が育っていきます。
やめさせる?続けさせる?判断の分かれ道
続けるメリットとやめるメリット
習い事をやめるか続けるか―
―親としてはとても悩ましい問題です。続けることで得られるものもあれば、無理に続けさせることで逆効果になることもあります。では、まずそれぞれのメリットを整理してみましょう。
【続けるメリット】
-
忍耐力や継続力が身につく
-
やり続ける中でできる喜びや自信を得られる
-
仲間や先生との関係性から社会性が育つ
-
努力が成果に結びつく経験ができる
【やめるメリット】
-
無理なストレスから解放される
-
新しいことにチャレンジする時間ができる
-
本人の「やりたい」を優先できる
-
本当の適性や興味を見つけやすくなる
重要なのは、「ただなんとなくやめさせる」「気合で続けさせる」ではなく、
子供の性格や状況に応じて、どちらが将来的にプラスになるかを見極めることです。
また、やめることを「逃げ」や「失敗」と思わせない工夫も必要です。
「次に進むための一歩」と捉えさせてあげましょう。
「一時的なイヤ」と「本気の拒否」の見極め方
子供が「行きたくない」と言うとき、それが一時的な感情なのか、
それとも本当に苦痛を感じているのかを見極めることが大切です。
【一時的なイヤのサイン】
-
前日までは楽しそうに通っていた
-
体調や気分によって気まぐれに言う
-
行った後は「楽しかった」と言う
-
家では習い事の練習をしている
【本気の拒否のサイン】
-
毎回行く前に泣く・体調を崩す
-
習い事の話題を避けたがる
-
家でも練習や話をまったくしない
-
自己評価が著しく低くなっている
親が注意深く観察することで、どちらなのか判断しやすくなります。特に、長期的な変化(以前は好きだったのに徐々に嫌がるようになった等)には要注意です。
行かせて無理をさせることが、子供にとってトラウマになってしまうこともあります。逆に、「行ってみたら楽しかった」ということもあるので、その判断は慎重に行いましょう。
判断を誤らないための親のチェックリスト
習い事をやめさせるかどうか悩んだときには、以下のようなチェックリストを使ってみると、
冷静な判断がしやすくなります。
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 習い事の前後に機嫌が悪くなることが続いている | ✅ | |
| 練習や課題に対する意欲が明らかに落ちている | ✅ | |
| 先生や仲間との関係に悩んでいる様子がある | ✅ | |
| 子供が自分の気持ちを説明しようとしている | ✅ | |
| 他にもっと興味を持っていることがある | ✅ | |
| 続けることに意味を感じていないように見える | ✅ |
「はい」が多ければ、一度習い事の見直しを考えてみるのがよいでしょう。子供の様子と、
家庭の状況もふまえて、柔軟に対応していくことが大切です。
習い事の先生に相談すべきタイミング
子供のことで悩んでいるとき、頼れる存在のひとつが「習い事の先生」です。
プロの視点から、親とは違った角度で子供の様子を見てくれている場合があります。
相談するタイミングとしては、以下のようなときが適しています。
-
子供が継続的に嫌がるようになった
-
技術的な伸び悩みが目立ってきた
-
人間関係に問題があるかもしれないと感じた
-
親子だけでは解決が難しいと感じた
先生に相談するときは、「やめるか続けるか」という話に急がず、まずは「最近の様子で気になることがあります」と前向きに切り出すのがポイントです。話すことで、先生も子供への対応を見直してくれることがあり、状況が改善する可能性もあります。
親子で納得できる結論を出すコツ
最後に一番大事なのは、親が一方的に決めるのではなく、
「子供と一緒に」答えを出すことです。
子供に選択の余地を与えることで、納得感が生まれます。「嫌ならやめればいい」ではなく、「どうしたいと思っているのか」「そのために何ができるか」を一緒に考える時間をつくってみましょう。
話し合いの中で、子供が自分の気持ちを整理できたり、意外な本音が出てきたりすることもあります。そして親がその気持ちを受け止めてくれたと感じたとき、子供は安心して次の一歩を踏み出せるのです。
選択を急がず、子供のペースに寄り添いながら、
親子で納得のいく結論を導いていきましょう。
子供のやる気を引き出す声かけ術
禁句ワードとNG対応とは?
子供が習い事に行きたくないと言ったとき、つい言ってしまいがちな言葉がありますが、それが
やる気をさらに失わせてしまうことがあります。特に注意したいのが以下のような言葉です。
-
「なんで行きたくないの?」
-
「せっかくお金払ってるのに」
-
「やめたら将来困るよ」
-
「他の子はちゃんと行ってるよ」
これらの言葉は、子供を責めたり、親の都合を押しつけたりしてしまうNG対応です。子供は
「自分の気持ちをわかってもらえない」と感じ、ますます心を閉ざしてしまいます。
また、強引に引っ張って無理やり連れて行ったり、泣いている子供を「がんばれ!」と叱咤するのも逆効果です。こうした対応は「習い事=嫌なもの」という印象を強くしてしまいます。
まず大切なのは、子供の気持ちに寄り添ってあげること。「そう思うんだね」「今日は行きたくない気分なんだね」と受け止めるだけでも、子供の気持ちは少しずつ落ち着いていきます。
親の対応ひとつで、子供のやる気は大きく左右されるのです。
「できた!」を引き出す魔法の言葉
子供のやる気を引き出すには、小さな成功体験を積ませることが何より効果的です。そして、
その成功をしっかり認める「魔法の言葉」がやる気の火を灯します。
たとえば、
-
「昨日より速く走れたね!」
-
「前より上手にできてたよ!」
-
「がんばって練習したのがわかるよ」
-
「途中で諦めずにすごい!」
など、「結果」ではなく「過程」を褒めることがポイントです。
子供は、親に認めてもらえることで、「またやってみよう」と思えるようになります。
特に「前より成長したね」と言ってあげることで、子供自身も自分の変化に気づくことができ、
自信につながります。
このような言葉を日常的にかけることで、習い事に対する前向きな気持ちが育ちます。
子供のやる気の芽は、親の言葉ひとつで大きく育つのです。
子供の自己肯定感を育てる褒め方
自己肯定感が高い子は、多少うまくいかないことがあっても「大丈夫、自分ならできる」と
前向きに取り組むことができます。そのためには、日常の中での「褒め方」がとても大切です。
ポイントは以下の3つ。
-
具体的に褒める
×「すごいね!」
〇「最後までやりきったのがすごいね!」 -
できたことだけでなく努力も褒める
×「ピアノうまいね」
〇「毎日少しずつ練習していた成果が出てるね」 -
比較しないで、その子自身を見て褒める
×「〇〇ちゃんより上手だね」
〇「昨日の自分より上手になったね」
褒められた経験が「自分には価値がある」という感覚を育てます。そして、
それが「やる気」と「挑戦する力」につながります。
自己肯定感は一度つけば一生の宝物になります。
褒める習慣は、家庭で毎日できる最高の子育て法です。
目標の立て方ひとつで変わる気持ち
子供が習い事にやる気を持つためには、「自分で立てた目標」があると効果的です。大人でもゴールが見えないとモチベーションが下がるように、子供も「何のためにやってるの?」と感じてしまいます。
ここでのコツは、「小さくて具体的な目標」を一緒に考えることです。
たとえば、
-
「今月は縄跳びを30回飛べるようになろう」
-
「来週のレッスンでは先生に一度も注意されないようにしよう」
-
「ピアノのこの一曲だけは完璧に弾けるようにする」
このように、達成しやすい目標にすることで、「できた!」という達成感を
何度も味わわせてあげましょう。
さらに、「一緒にカレンダーにシールを貼る」など、見える形で記録をつけると、
目標に向けた行動が楽しくなります。
目標を持つことで、習い事が「自分のためのもの」へと変化し、
やる気もぐんと高まります。
習い事を生活の中に自然に取り入れる方法
習い事は、日常と切り離された「特別なこと」だと思うと、子供にとって負担になることが
あります。逆に、生活の中に自然に取り入れられると、楽しんで続けやすくなります。
たとえば、
-
音楽なら、家でもお気に入りの曲をかける
-
英語なら、朝の挨拶を「Good morning!」にしてみる
-
体操なら、お風呂上がりにストレッチを一緒にする
こうした「遊び感覚で触れられる時間」があるだけで、子供の意識が大きく変わります。
「やらなきゃいけないこと」ではなく、「やってみたいこと」に変えてあげる工夫が必要です。
また、親も「楽しそうだね」「見せてくれてありがとう」と興味を持つことで、子供はますます習い事に前向きになります。生活の中に溶け込ませることで、子供にとって習い事は「自然な一部」となり、無理なく続けられるようになるのです。
あなた:
Magic AI-ブログライター の発言:
他の子と比べない「うちの子らしさ」を伸ばす考え方
成長スピードはみんな違って当たり前
子供の成長には個人差があります。
これは、身長や体重のような身体的なことだけでなく、理解力、集中力、運動神経、感情の表現力などすべてにおいて言えることです。それにも関わらず、親はつい「他の子はもう〇〇できるのに…」と比べてしまいがちです。
でも、子供はそれぞれ自分のペースで成長していくもの。早くできることがすごいのではなく、
続けたことで少しずつ上達する力の方が大事です。芽が出るタイミングが違うだけで、コツコツ取り組めば、ある日グッと伸びる瞬間が必ず訪れます。
習い事では特に、同じ年齢の子と一緒に活動することが多いため、比べてしまいやすい環境です。でも親が「うちの子はうちの子」と信じて見守ることで、子供も安心して自分らしく頑張ることができます。
親の「待つ力」が、子供の「育つ力」を引き出すのです。
比較がもたらすデメリットと心理的影響
他の子と比べられることが続くと、子供はどうなるでしょうか?
「どうせ自分はできない」「お母さんはあの子の方が好きなんだ」と感じてしまい、
自己肯定感が大きく下がる原因になります。
特に繊細な子や真面目な子ほど、「比べられること=自分が劣っている証拠」と捉えてしまいがちです。すると、チャレンジすることを避けたり、新しいことを怖がったりするようになります。
親のちょっとした一言でさえも、子供にとっては深く刺さるもの。「〇〇ちゃんみたいにやってごらん」ではなく、「あなたはあなたのやり方で大丈夫」と伝えることが、子供の心を強くしていきます。
比べることは親の不安を解消する手段に過ぎません。子供の心を守るためには、
「比べない」勇気も必要です。
子供の得意を見つける観察ポイント
「うちの子、何が得意なんだろう?」と悩む親も多いですが、
実は日常生活の中にヒントはたくさんあります。
観察するポイントは以下のようなところです:
-
集中して取り組んでいる時間が長いもの
-
自然と笑顔になる場面
-
誰に言われなくても自主的にやっていること
-
失敗しても何度もチャレンジする姿勢が見られるもの
-
お友達に教えたがるような内容
こうした場面を見つけたら、それを「得意のタネ」として育てていくと良いでしょう。
得意なことに気づき、自信を持つと、他の分野でも前向きな姿勢が育ちやすくなります。
「他の子と比べて優れているか」ではなく、「その子が自然に力を発揮できること」に
注目する視点を持ちましょう。
習い事よりも大切なことって?
親はどうしても「何か習わせなきゃ」「スキルを身につけさせなきゃ」と考えがちですが、
実は子供にとって習い事以上に大切なことがあります。
それは、「自由に過ごす時間」「親との信頼関係」「自分を受け入れてもらえる安心感」です。
習い事に行くことがストレスになってしまうと、これらの大切な要素が削られてしまうこともあります。
何かに熱中したり、友達と遊んだり、好きなことで没頭したりする時間も、子供の成長には欠かせません。また、親が一緒に笑ったり、失敗を受け止めてあげたりする日常のやり取りの中で、子供の「心の土台」は育っていきます。
習い事はあくまで「手段」であって「目的」ではありません。
「習い事を通じて何を得てほしいか?」を改めて考えてみましょう。
子供の「好き」を一緒に見つける時間の大切さ
子供が何かに夢中になる力、「好き!」と思える気持ちは、将来の人生を大きく左右する原動力になります。でもその「好き」は、最初から見つかっているわけではありません。親と一緒にいろいろな体験をする中で、少しずつ形になっていくものです。
たとえば、
-
一緒に本屋でいろんなジャンルの本を手に取ってみる
-
無料体験のイベントに参加してみる
-
動物園や科学館、美術館などで反応を観察する
-
お友達の習い事の発表会に行ってみる
こういった体験を通じて、「なんか楽しそう」「これ面白い!」という気持ちが芽生えることがあります。その芽を見逃さず、「それやってみる?」と声をかけるだけで、子供の可能性が大きく広がっていきます。
一緒に「好き」を探す時間は、親子の絆も深めてくれます。何より、
「子供の世界を一緒に楽しもうとする姿勢」が、子供の心を豊かに育てるのです。
習い事との上手な付き合い方|親子で楽しむコツ
習い事の選び直しは悪いことじゃない
「せっかく始めたのに…」と、習い事をやめることに罪悪感を感じる親は多いですが、習い事の選び直しは決して悪いことではありません。むしろ、子供の成長や興味の変化に合わせて選び直すのは、自然で前向きなことです。
例えば、最初は体操に夢中だった子が、ある日「絵を描くのが好きかも」と気づくこともあります。それを「また変えたいの?飽きっぽいね」などと否定してしまうと、子供は自分の興味や好奇心を表現しにくくなります。
「いろんなことにチャレンジして、自分に合うものを探す」という姿勢は、将来の自立や選択力にもつながります。親は、「方向転換」=「失敗」ではなく、「学び直し」や「発見のチャンス」として受け止めましょう。
習い事は、子供にとって「自分らしさ」を探す旅。その旅に寄り添ってあげることが、
親の最大のサポートです。
習い事を通じて育てたい5つの力
習い事を続ける目的は、単なるスキルの習得だけではありません。そこから得られる
「人としての力」が、子供の将来に役立つ大きな財産になります。
以下は、習い事を通じて育まれる5つの力です。
| 育つ力 | 説明 |
|---|---|
| 継続力 | 苦手なことにも向き合い、努力し続ける力 |
| 自己肯定感 | 成長や成功を通じて「自分はできる」と思える力 |
| 協調性 | チームや仲間との関わりの中で育つコミュニケーション力 |
| 表現力 | 自分の気持ちや考えを形にする力(芸術や音楽など) |
| 判断力 | 自分で考えて行動する経験から育まれる力 |
これらは学校の成績では測れない「生きる力」です。
たとえ習い事が上達しなくても、こうした力が身につけば、それだけで大成功と言えます。
親は、技術や成果だけでなく、その過程で
どんな力が育っているかを見つめてあげることが大切です。
親も一緒に学ぶスタンスがカギ
子供が習い事を続ける上で、親の関わり方が大きな影響を与えます。特に、「教える」「監督する」というより、「一緒に学ぶ」「応援する」というスタンスが、子供のやる気を育てます。
たとえば、
-
習ったことを見せてもらって「教えて~」と言ってみる
-
レッスンの帰り道に「今日、楽しかったところは?」と聞いてみる
-
発表会や試合を一緒に楽しんで観る
こうした姿勢は、「自分のやっていることに親が関心を持ってくれている」と子供に感じさせ、
モチベーションを高める大きな力になります。
また、親が失敗や挑戦に対して寛容であることも大切です。
「失敗してもいい」「やり直せる」「続けることが大事」といった考え方を、
親の言動で伝えていきましょう。
習い事は、子供だけの挑戦ではありません。
親子で一緒に成長していく学びの時間でもあるのです。
習い事以外の時間の過ごし方も見直そう
習い事ばかりに意識が向きがちですが、実はそれ以外の時間の過ごし方も、
子供の心と体のバランスに大きく影響します。
毎日ぎっしりと予定が詰まっていると、子供は休む間もなく、結果的に習い事にも嫌気がさしてしまいます。また、自由に遊ぶ時間が減ることで、創造力や自己表現力が育ちにくくなることもあります。
習い事を長く楽しく続けるためには、「何もしない時間」「ダラダラする時間」「自由に遊ぶ時間」も大切にする必要があります。こうした時間の中で、子供は自分自身をリセットし、次の活動へのエネルギーを蓄えるのです。
スケジュールに「余白」をつくることで、子供も親も心にゆとりが生まれ、
習い事とのバランスも良くなります。
無理をさせない関わり方とは?
習い事に関して一番大事なのは、子供に無理をさせないことです。無理に頑張らせると、体調を崩したり、やる気を失ったりするだけでなく、「自分の気持ちより親の期待を優先しなければいけない」と思い込んでしまう危険性もあります。
とはいえ、「行きたくない」と言われるたびにすぐ休ませるのも考えものです。大切なのは、子供のサインをしっかり読み取り、「どこまでが頑張りどころで、どこからが無理なのか」を親が判断することです。
そのためには、日々の体調や表情、言葉遣いをよく観察しましょう。「最近、疲れてる?」「何か心配なことある?」と、声をかけるだけでも、子供は安心して本音を話せるようになります。
無理をさせないというのは、甘やかすことではなく、
「その子の心と体の声に耳を傾けること」です。
信頼関係を築くことで、子供は自分から前に進もうとする力を育んでいきます。
まとめ|習い事は「親子で育つ」チャンス
子供が「習い事に行きたくない」と言い出したとき、それは単なるワガママではなく、心の中にある大切なサインです。その気持ちをしっかり受け止め、子供の声に耳を傾けることで、親子の信頼関係はより深まります。
習い事は、上達や成果だけが目的ではありません。続けることで得られる力、途中でやめたことから得る気づき、そして新しいことにチャレンジする勇気――どれもが子供にとって大きな財産です。
親が「他の子と比べる」のではなく、「わが子のペース」を尊重することで、子供は自分を信じる力を育てていきます。そして、親もまた、子供の成長を通じて多くの学びを得るのです。
習い事は「親子で育つ」貴重なチャンス。無理なく、楽しく、
そして心から応援できる関わり方を、ぜひ見つけてみてください。