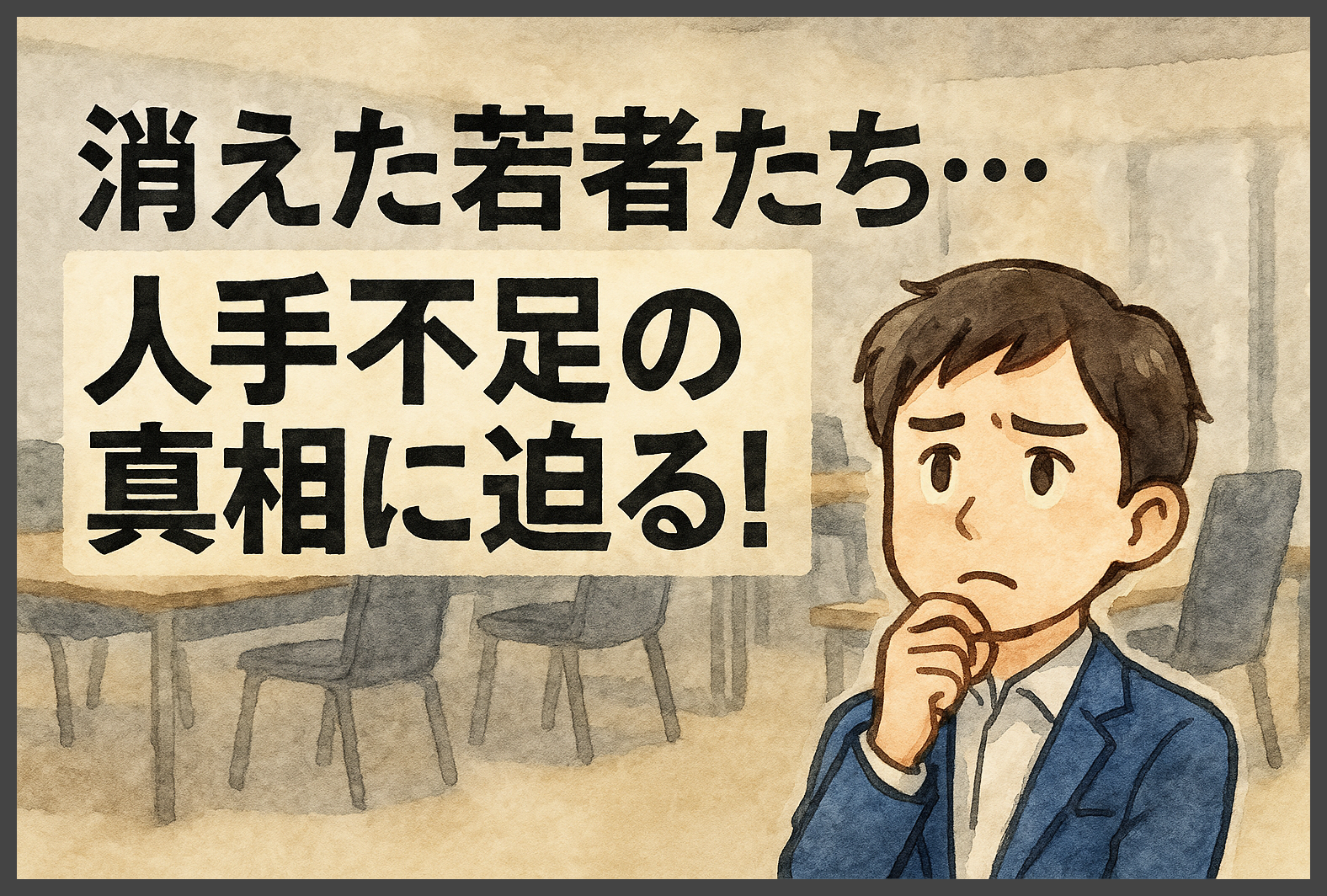人手不足が深刻なのに、若者の姿がなかなか見えない。
いったい今の若者はどこへ行ってしまったのでしょうか?
「若者が働かないって本当?」
「昔と比べて職場が変わったの?」
「なぜこんなに人手が足りないの?」
こういった疑問や悩みに答えます。
この記事では、人手不足の背景や若者の働き方の変化をわかりやすく解説しています。
今の現場で起きていることや、若者の新しい価値観、そして未来に向けたヒントが見えてきますよ。
人材確保に悩むあなたや、「なんで人が来ないの?」
と感じているすべての方に読んでほしい内容です。
人手不足 若者 どこへ?背景と現実を徹底解説
人手不足が深刻なのに、若者の姿が現場から消えている——そんな疑問に迫ります。
- ①若者が選ばない仕事の特徴
- ②現場から見た人手不足の実態
- ③働く世代の価値観の違い
- ④統計で見る若者の労働参加率
①若者が選ばない仕事の特徴
人手不足が叫ばれる業界には、なぜ若者が集まらないのでしょうか。
それは「きつい・汚い・危険」とされるいわゆる3Kの仕事が多いことが一因です。
介護、建設、飲食などは体力的にも厳しく、しかも低賃金で評価されにくい現状があります。
また、キャリアアップの道が見えづらい、将来が不安という声も多数。
こうしたイメージが若者の選択肢から外れてしまう大きな理由なのです。
②現場から見た人手不足の実態
では、現場ではどんな課題が起きているのでしょう。
建設業界では、定年後も70歳を超えて現場に立つ職人が多数います。
介護施設では夜勤明けでも人手が足りず、休みなしで働く職員も珍しくありません。
飲食店では求人を出しても1人も応募がないという話もあるほどです。
現場はまさに“猫の手も借りたい”状態なのです。
③働く世代の価値観の違い
若者が求める働き方と、今の職場の在り方が合っていないケースも多いです。
たとえば、今の20代は「やりがい」「自由」「自分らしさ」を大切にします。
一方、現場仕事は「拘束時間が長く」「ルーティンが多い」「評価が曖昧」な職場が多いのです。
この価値観のギャップが、採用や定着の壁になっています。
ただ給料が高いだけでは、若者の心は動かない時代なのです。
④統計で見る若者の労働参加率
総務省の労働力調査(令和5年)によると、15〜24歳の労働参加率は年々減少しています。
また、非正規雇用の割合が増え、正社員志向は下がっています。
以下の表で近年の変化をまとめてみました。
| 年度 | 労働参加率(15〜24歳) | 非正規率 |
|---|---|---|
| 2010年 | 55.3% | 28.1% |
| 2020年 | 50.8% | 32.4% |
| 2023年 | 48.9% | 35.0% |
このデータからも、若者の「フルタイム就職離れ」が進んでいるのが分かりますね。
人手不足の現場で起きている5つの変化
人手不足の深刻化により、現場ではさまざまな対策や変化が見られます。
- ①外国人労働者の増加
- ②ロボットや自動化の導入
- ③企業の採用戦略の変化
- ④ベテラン世代の延命雇用
- ⑤非正規雇用の常態化
①外国人労働者の増加
近年、日本の現場労働を支えているのは外国人労働者とも言えます。
技能実習制度や特定技能制度により、アジア圏を中心に多くの若者が来日しています。
しかし、言語や文化の壁、労働環境の厳しさで離職も多いのが現実です。
日本の人手不足を補うには欠かせない存在ですが、永続的な解決策にはなりません。
②ロボットや自動化の導入
人手が足りないなら機械で補う!という動きも加速しています。
たとえば、飲食では配膳ロボット、建設ではドローン測量、介護では見守りセンサーなどが登場。
しかし、導入コストや技術的なサポートがネックとなり、中小企業にはまだ普及しきれていません。
人手不足と同時に「DX人材不足」も課題となっているのです。
③企業の採用戦略の変化
今までのような「求人を出せば応募がある」という時代は終わりました。
最近はSNSでの企業紹介や、YouTubeでの会社紹介なども積極的に行われています。
求職者との接点を増やすため、企業も広報力を高める必要があるのです。
選ばれる会社になるには、ブランディングが欠かせません。
④ベテラン世代の延命雇用
高齢者の働き手が「最後の砦」として現場を支えています。
定年延長や再雇用制度を使い、70代まで働く人も珍しくありません。
もちろん体力的な問題もありますが、技術継承の面では重要な存在。
ただし、未来を担う若者がいなければ、産業そのものの持続性が危うくなります。
⑤非正規雇用の常態化
人手を確保するために、非正規や派遣に頼る企業が増えています。
フルタイムの正社員が減り、シフトや短時間勤務のパートタイム中心に。
柔軟な働き方ができる反面、定着率の低さやモチベーションの維持が課題です。
一時しのぎにはなっても、根本的な解決には繋がりません。
若者はどこへ?見えない労働力の行方
若者が人手不足の現場にいないなら、いったいどこで働いているのでしょうか。
- ①フリーランス志向の高まり
- ②YouTuberやインフルエンサー志望
- ③副業・複業を前提とした働き方
- ④地方移住や田舎ワークの選択
①フリーランス志向の高まり
最近の若者は「安定よりも自由」を選ぶ傾向が強いです。
クラウドソーシングやSNSを活用し、フリーランスとして働く人が急増しています。
時間や場所に縛られず、自分のスキルで稼げる働き方が魅力なんですね。
特にデザイナー、ライター、動画編集者など、オンラインで完結する仕事が人気です。
②YouTuberやインフルエンサー志望
「子どものなりたい職業ランキング」にも登場するYouTuberやTikToker。
発信力がそのまま収入に変わる時代になり、自己表現を重視する若者が増えています。
彼らは“好き”を仕事にできる可能性を持っています。
会社員という枠にとらわれず、自分のブランドを築こうとしているんですね。
③副業・複業を前提とした働き方
「ひとつの仕事に依存したくない」という考えも広がっています。
本業×副業、会社員×週末起業、という複業スタイルを選ぶ人も増加中。
この背景には、終身雇用の崩壊や経済的不安があると言われています。
若者はリスクを分散しながら、自分らしく働く方法を模索しているのです。
④地方移住や田舎ワークの選択
コロナ以降、都市圏から地方へ移住する若者も目立ってきました。
自然豊かな場所でリモートワークをしたり、地域おこし協力隊として働いたり。
暮らしの質を大切にするライフスタイルへの転換が起きています。
若者が「自分にとって本当に大切なもの」を見つめ直している証拠かもしれませんね。
若者を惹きつける職場の5つの条件
人手不足を解決するためには、若者に「働きたい!」と思ってもらえる職場づくりが重要です。
- ①柔軟な働き方の提供
- ②やりがいと自己成長の重視
- ③ITスキルやSNS活用
- ④社内コミュニティの魅力
- ⑤報酬だけでない「幸福度」
①柔軟な働き方の提供
若者が重視するのは、時間や場所に縛られない働き方です。
リモートワーク、フレックス制、副業OKなどがある企業は人気が高い傾向にあります。
ワークライフバランスを保てる環境が、職場選びの大きなポイントになっています。
「働きやすさ」は採用活動の競争力になる時代です。
②やりがいと自己成長の重視
給料よりも「やりがい」や「スキルアップ」を重視する若者も多いです。
そのためには、明確なキャリアステップや社内研修制度があることが重要です。
挑戦を歓迎する文化や、フィードバック体制がある企業は評価されます。
「成長できる職場」は、今後さらに注目されるキーワードになりそうですね。
③ITスキルやSNS活用
デジタルネイティブ世代にとって、テクノロジーの活用は当たり前です。
業務のデジタル化や、社内SNSの活用などが進んでいると、若者は親しみやすさを感じます。
逆に「紙で管理」「電話でやりとり」などは敬遠されがちです。
職場環境そのものが“デジタル時代に合っているか”が大事な要素になってきます。
④社内コミュニティの魅力
仲間とのつながりや、職場での人間関係も大切なポイントです。
フラットな組織構造や、部活動、オンラインイベントなどがあると好印象につながります。
「誰と働くか」が重視される時代、安心できる職場づくりが鍵になります。
コミュニケーションの工夫が、採用にも直結するんですね。
⑤報酬だけでない「幸福度」
近年では、年収よりも「働いていて幸せか」が重視されています。
福利厚生やメンタルサポート制度、社風などが評価の対象になることも。
働くこと=つらい、という価値観はすでに古くなりつつあります。
企業も「幸福度経営」に取り組む必要が出てきました。
人手不足を解決するための新しいアプローチ
最後に、人手不足という社会問題にどう向き合うべきかをまとめます。
- ①企業の意識改革とDX
- ②教育機関との連携強化
- ③政府による構造的対策
- ④若者の声を活かす制度設計
①企業の意識改革とDX
まず必要なのは、企業側の「変わる努力」です。
働き方の見直しや、業務のデジタル化、従業員へのリスペクトが不可欠です。
「来てくれない」ではなく「選ばれる会社になる」ことが重要ですね。
その第一歩がDXの導入です。
②教育機関との連携強化
学校と社会のミスマッチも課題のひとつです。
インターンや職業体験を通じて、仕事の魅力を若いうちから伝える必要があります。
企業と教育機関が連携して、職業理解を深める機会を増やしましょう。
リアルな仕事観を伝えることが、将来の人材確保につながります。
③政府による構造的対策
少子化や高齢化に対応するため、政府の本格的な支援が求められています。
働くインセンティブのある税制度や、育児・介護との両立支援が不可欠です。
外国人労働力との共存も制度設計がカギを握ります。
「人手不足は自己責任」では済まされない時代になってきました。
④若者の声を活かす制度設計
最後は“当事者”である若者の声を聞くことです。
採用面接での一方通行ではなく、職場改善へのフィードバック制度があるとよいでしょう。
「何があれば働きたいか」を真剣に聞く姿勢が、未来を作るカギになります。
制度設計には、実際の声とニーズを反映させるべきです。
今回は「人手不足 若者 どこへ?」というテーマで、若者が職場にいない理由や、
現場で起きている変化を深掘りしてきました。
昔とは違って、若者たちは“自由”や“成長”“心地よさ”を大事にして働き方を選んでいます。
だからこそ、ただ「来てくれない」と嘆くよりも、若者に選ばれる職場を
どう作っていくかがカギになります。
企業の工夫、社会全体のサポート、そして若者自身の声。
それぞれが重なりあってこそ、未来の働き方がもっと明るくなるはずです。
今こそ、「どうすれば一緒に働けるか?」を本気で考えるときなのかもしれませんね。