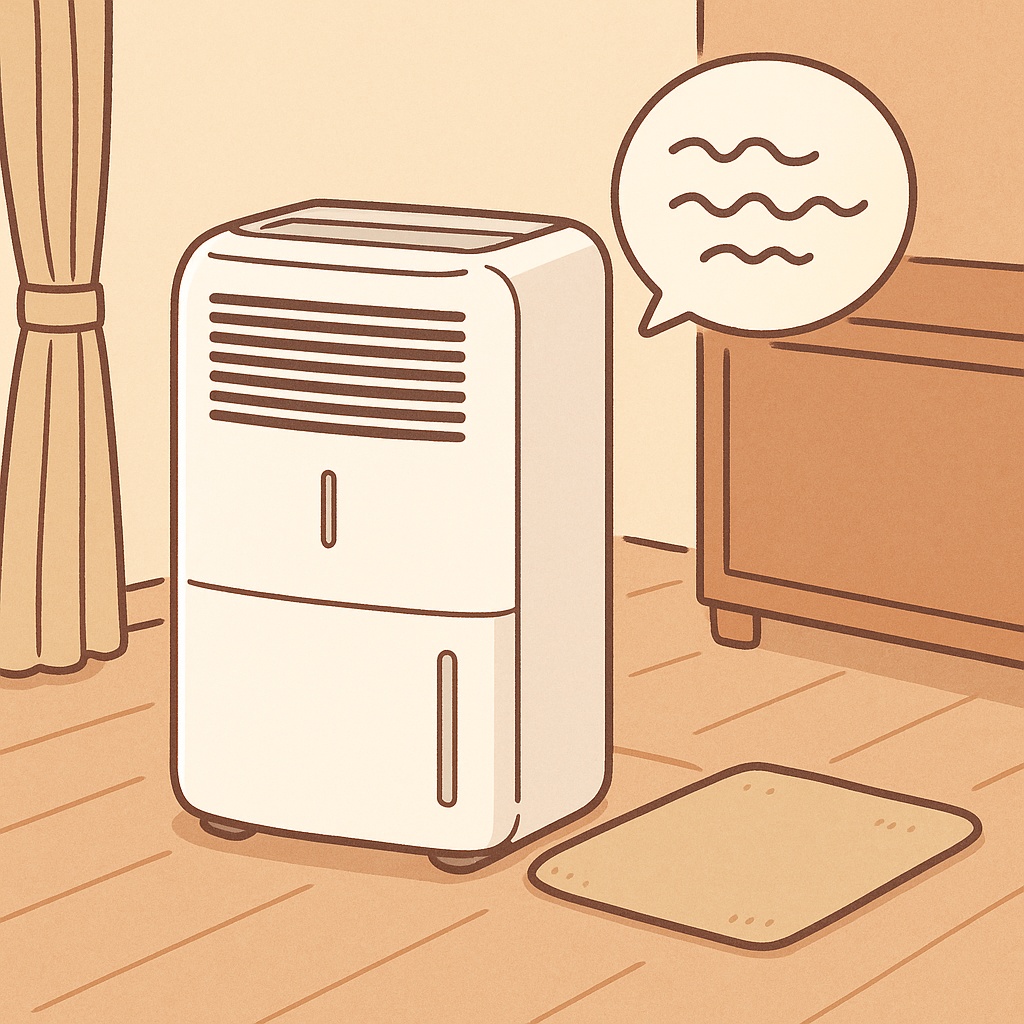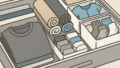梅雨や夏場に欠かせない除湿器。
でも、「うるさくて眠れない」「リビングで使うとテレビの音が聞こえにくい」といったお悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?特にコンプレッサー式除湿器は、その高い除湿力の反面、動作音や振動が気になることがあります。
そこで本記事では、「除湿器の音がうるさい!」という悩みに対して、原因の解説から今すぐできる静音対策、さらには静かな除湿器の選び方まで、徹底的に分かりやすく解説します。静かな暮らしを取り戻すために、ぜひ参考にしてください。
なぜ除湿器はうるさいの?仕組みを知って静音対策!
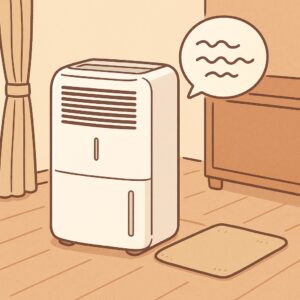
コンプレッサー式除湿器の仕組みとは
コンプレッサー式除湿器は、空気を冷やして湿気を水に変える仕組みです。エアコンと同じような仕組みで、空気を吸い込んで内部で冷却し、水分を取り除いた空気を再び部屋に戻します。このとき、内部のコンプレッサー(圧縮機)が動くことで冷却を行っています。
コンプレッサーは機械的な部品なので動作時に「ブーン」という音や振動を発生させます。これが「うるさい」と感じる一番の原因なのです。とくに夜間や静かな部屋で使用すると、音が響いて気になることがあります。除湿力が強いほどコンプレッサーもパワフルになるため、音も大きくなりがちです。
騒音の主な原因はどこ?
除湿器の音の原因は、大きく分けて3つあります。まずひとつ目は「コンプレッサーの駆動音」。先ほど説明したように、除湿のために圧縮機が作動する音です。ふたつ目は「送風ファンの音」。空気を吸い込んで排出するためにファンが回転しており、この風切り音が「ゴーッ」と響くことがあります。
そして三つ目が「本体の振動音」。除湿器が床や家具に接触していると、振動が伝わって不快な音に感じられるのです。これらの音が重なることで、思った以上に「うるさい」と感じてしまう人が多いのです。
モーター音と振動音の違い
モーター音とは、コンプレッサーやファンを動かすための電動モーターが発する「機械音」です。これは製品の構造や部品の品質によって変わります。静音設計されていないモデルでは、モーター音が強く出てしまう傾向があります。
一方、振動音は本体が床や壁などに接触していて、その振動が響くことで「ガタガタ」「ブーン」といった音に変わる現象です。モーター音は内部から発生するため軽減しにくいですが、振動音は設置方法を工夫することで改善できる可能性が高いです。音の種類を見分けることが対策の第一歩になります。
気温と音の関係
実は、気温によっても除湿器の動作音は変わってきます。コンプレッサー式除湿器は気温が高いと効率よく除湿できますが、気温が下がると除湿効率が落ち、逆にコンプレッサーが頑張って動こうとするため、動作音が大きくなりがちです。
特に梅雨明け後や秋口の少し肌寒い時期には、音が目立つと感じることがあります。また、冷たい空気が内部で結露しやすくなることで、定期的に霜取り運転が始まり、その際にも「カチッ」「ブーン」といった異音がすることがあります。
静音性能の高い除湿器とは?
最近では「静音性」を重視した除湿器も多く販売されています。静音性能が高いモデルは、コンプレッサーの稼働音が抑えられていたり、ファンの回転数が低く設定できたりします。また、内部構造や部品の素材に工夫がされており、モーターやファンの音を吸収するような設計になっているのが特徴です。
製品の仕様には「騒音レベル(dB)」が記載されていることが多いので、購入時にはこの数値をチェックしましょう。目安としては、40dB以下であれば比較的静かで、30dB前後になると図書館並みに静かと言われています。
今すぐできる!除湿器のうるさい音を軽減する簡単対策5選
ゴムマットで振動を吸収しよう
除湿器の下にゴムマットや防振マットを敷くだけで、床に伝わる振動音がぐっと抑えられます。これは特にフローリングや板の間に設置している場合に効果的で、「ブーン」「ガタガタ」といった音が小さくなることがあります。
ゴム素材は音の伝達をやわらげる性質があるため、家電の騒音対策として広く使われています。100円ショップやホームセンターでも手軽に手に入るため、費用対効果が高い方法といえるでしょう。特に夜間使用する人には、簡単に静音化できるアイテムとしておすすめです。
壁との距離を確保して反響音を減らす
除湿器を壁にピッタリくっつけて置いていると、音が壁に反響して「余計にうるさく」聞こえてしまうことがあります。これは「音の反射」といって、音波が壁で跳ね返って戻ってくることで起こる現象です。これを防ぐには、除湿器を壁から10〜20cmほど離して設置するのがポイントです。
また、部屋の角に置くのも避けた方が良いです。角は音が集中しやすく、反響音が強くなるため、音のボリュームが倍増して感じることもあります。空間に余裕を持って設置することで、騒音のストレスが減る可能性があります。
モード設定を「弱」に切り替える
除湿器には多くの場合、「強」「中」「弱」や「静音」などのモードが用意されています。強モードは短時間で除湿できますが、コンプレッサーやファンが全力で動作するため、当然ながら音も大きくなります。
一方、弱モードや静音モードに切り替えることで、動作音をかなり抑えることが可能です。除湿スピードはゆるやかになりますが、夜間や在宅中など音が気になるタイミングには、こうしたモードを使い分けるのが効果的です。状況に応じた使い方をすることで、快適さと静けさを両立できます。
フィルターの掃除で風切り音を減らす
除湿器のフィルターにホコリが溜まっていると、空気の通り道が狭くなり、風切り音が大きくなることがあります。「ゴーッ」「ヒューヒュー」といった耳障りな音がする場合は、まずフィルターの掃除をしてみましょう。
多くの除湿器はフィルターが取り外し可能で、水洗いできるタイプもあります。月に1回程度の掃除を目安にすれば、風通しも良くなり、運転音も改善される可能性があります。フィルターがきれいだと除湿効率もアップするので、一石二鳥の対策です。
タイマーや湿度設定で稼働時間を調整
ずっと動かしっぱなしにしていると、当然音も長時間出続けることになります。これを防ぐために、除湿器に搭載されている「タイマー機能」や「湿度設定」を活用しましょう。
例えば夜間だけ稼働するようにタイマーをセットしたり、「湿度60%を下回ったら停止する」といった設定にしておくことで、稼働時間と音の発生時間をコントロールできます。無駄な動作が減るため電気代の節約にもなりますし、音のストレスも軽減されて一石二鳥です。
静かな除湿器に買い替えたい人向け!選び方のポイント

コンプレッサー式vsデシカント式の違い
除湿器には大きく分けて「コンプレッサー式」と「デシカント(ゼオライト)式」の2種類があります。コンプレッサー式は冷却方式で、電気代が安くて夏場に強いのが特徴ですが、動作音が比較的大きいです。
一方、デシカント式は乾燥剤を使って湿気を吸い取る仕組みで、ヒーターを使うため音が静かですが、電気代が高くなりがちです。静かさを重視するなら、デシカント式のほうがおすすめです。特に寝室や赤ちゃんのいる部屋で使うなら、音の静かさはとても重要なポイントになります。
dB(デシベル)表示をチェックしよう
除湿器を選ぶときには、商品のスペックに書かれている「騒音レベル(dB)」をしっかり確認しましょう。一般的に、40dBは静かな住宅街、30dBは図書館レベルの静かさと言われています。目安としては、40dB以下の除湿器であれば多くの人にとって「静か」と感じられる範囲です。
最近の製品では、運転モードによって音の大きさが変わるため、最小運転時と最大運転時の両方のdB値を確認するのがベストです。静音性をうたう製品でも、実際には騒音レベルが高いケースもあるため、スペック表の確認は必須です。
寝室や子供部屋には「静音モード」がある機種を
寝室や子ども部屋など、音が特に気になる場所で除湿器を使う場合は、「静音モード」があるかどうかをチェックしましょう。静音モードでは、ファンの回転数を下げたり、コンプレッサーの動作をゆるやかにすることで、全体的な音を抑える工夫がされています。
たとえば、ある機種では通常時は約45dB、静音モードでは30dB以下に抑えられることもあります。こうした機能があると、夜間でも安心して使用できますし、赤ちゃんが眠る部屋にも向いています。
小型で静音設計のおすすめモデル
静音性を重視するなら、小型タイプの除湿器を検討してみましょう。最近では、10畳以下の部屋用に開発された小型モデルでも除湿力が十分で、しかも音が非常に静かな製品が増えています。
例えば、アイリスオーヤマの「静音除湿器」シリーズや、パナソニック、シャープなどの国産メーカーは信頼性も高く、レビューでも静かさが好評です。小型モデルは置き場所にも困らず、デザイン性も高いので、生活空間になじみやすいのも魅力です。
湿気対策と静音性のバランスを求める方におすすめです。
実際のレビューを参考にしよう
商品ページやカタログだけでは、実際の使用感はなかなか分かりにくいもの。そこで頼りになるのが、購入者のレビューです。「寝ている間でも気にならなかった」「予想以上に静かで満足」など、実際に使用した人の声はとても参考になります。
特にAmazonや楽天などの大手通販サイトでは、星の数だけでなく「音」に関する感想が数多く投稿されているので、購入前にしっかりチェックしましょう。メーカーサイトだけでなく、比較サイトやYouTubeのレビュー動画も役立ちます。
音が気になるときの応急処置とトラブルチェック方法

異音の種類とそれぞれの対処法
除湿器から「カチカチ」「ブーン」「ガラガラ」など、いつもと違う音が聞こえると不安になりますよね。これらの異音には、それぞれ原因があります。たとえば、「カチカチ」は霜取り運転時のリレー音、「ブーン」はコンプレッサーの動作音、「ガラガラ」は内部の部品のゆるみや異物の混入が考えられます。
異音がしたときは、まずマニュアルを確認し、製品特有の仕様かどうかをチェックしましょう。それでも解決しない場合は、メーカーのサポートに問い合わせるのが安全です。
本体の傾きが原因?設置場所の確認
除湿器の音が急に大きくなったり、ガタガタと振動がする場合は、本体がまっすぐ置かれていないことが原因かもしれません。床が斜めだったり、柔らかいカーペットの上に置かれていると、本体が不安定になり、振動音が増します。
また、キャスターがしっかりロックされていなかったりすると、動いてしまい音の原因になります。まずは水平な場所に設置し、しっかりと安定しているかを確認しましょう。設置環境を見直すだけでも、意外と音が静かになることがあります。
内部にゴミやホコリが詰まっていないかチェック
除湿器の吸気口や排気口にホコリやゴミが詰まっていると、空気の流れが悪くなり、ファンが余計に頑張って回ろうとするため、音が大きくなることがあります。特にペットの毛やキッチンの油分が多い家庭では、フィルターが汚れやすい傾向があります。
定期的に掃除機で吸ったり、水洗いが可能なタイプであれば洗って清潔に保ちましょう。メンテナンスを怠ると、除湿力も低下し、音もうるさくなる悪循環に陥るので注意が必要です。
長時間使用による経年劣化の可能性
除湿器も家電製品なので、長く使っていると部品が劣化し、音が大きくなったり異音が出たりすることがあります。特にコンプレッサーは消耗品なので、5年以上使用している機種で音がうるさくなったと感じた場合は、経年劣化のサインかもしれません。
こういったケースでは修理よりも買い替えを検討するほうが、静音性も除湿力も向上する可能性が高いです。最近の除湿器は省エネで静かな製品が多いため、思い切って新しいモデルにするのも一つの手です。
メーカーサポートに相談すべきケースとは
自分で対処しても音が改善されない、異音が続く、といった場合は、メーカーサポートに連絡するのがベストです。保証期間内であれば無償修理や交換対応をしてくれることもあります。
サポートに連絡する際は、購入時の情報や異音の発生タイミング、発生する音の種類などをメモしておくとスムーズです。また、異音の動画をスマホで撮っておくと、説明しやすくなります。無理に分解や修理を試みると保証が効かなくなることもあるので、注意が必要です。
除湿器の音が気にならない生活空間の作り方

家具配置で音の反響を防ぐ方法
除湿器の音が「響いてうるさい」と感じる原因の一つは、部屋の中で音が反響しているからです。特に家具が少ない部屋や、壁が硬くて音を跳ね返しやすい素材でできている部屋では、ちょっとした音でも大きく聞こえることがあります。
これを防ぐには、音を吸収してくれる「カーテン」「ラグマット」「ソファ」などの柔らかい家具を適度に配置するのが効果的です。家具が吸音材のような役割を果たし、音の広がりを抑えてくれます。除湿器の周囲に本棚や布製の家具を置くと、音の反射を分散できるのでおすすめです。
生活音に紛れるように設置する工夫
音が気になるのは、部屋が静かすぎるからということもあります。例えば、除湿器をテレビの近くや、普段よく話し声がする場所に置くことで、生活音に紛れて気にならなくなる場合があります。
逆に、静かな寝室や勉強部屋などに置くと、除湿器の音が目立ってしまいます。場所によっては、使う時間帯を工夫するのも一つの方法です。日中にリビングで使用し、夜はタイマーで停止させるなど、環境とタイミングに合わせて調整することで、音のストレスを軽減できます。
ドアや窓の防音対策と組み合わせる
外からの騒音が少ない家だと、逆に家電の音が目立って聞こえることがあります。そこで、ドアや窓からの音の出入りを防ぐ「防音対策」を取り入れるのも効果的です。防音カーテンや、すきまテープ、ドア下に敷く防音マットなどを使えば、室内の音も外に漏れにくくなり、反響音が抑えられます。
これにより除湿器の音が軽減されて感じることも。とくに集合住宅で「隣の部屋から
うるさいと言われた」といったケースでは、こうした対策が役立ちます。
静音家電で統一してストレス軽減
部屋にある家電の中で、1つだけ音がうるさいと、それがとても気になってしまいます。そこで、部屋全体の家電を「静音タイプ」でそろえることで、音のバランスが取れてストレスを感じにくくなります。
たとえば、空気清浄機、加湿器、サーキュレーターなども静音設計のものに替えると、部屋全体が静かになります。音のレベルがそろっていると、特定の音だけが浮き上がって聞こえることが減り、快適な生活空間を作ることができます。
除湿機能付きエアコンへの切り替えも検討
もし除湿器の音がどうしても気になる場合は、思い切って「除湿機能付きエアコン」を使う方法もあります。最近のエアコンは静音性が高く、除湿運転でもほとんど音がしないモデルが多くあります。
また、部屋の温度をあまり下げずに除湿だけを行う「再熱除湿」機能などもあり、冷えすぎることなく快適に湿気対策ができます。エアコンは天井に設置されているため、振動音や床に伝わる音もなく、音に敏感な人には特におすすめの選択肢です。
まとめ
除湿器の音がうるさいと感じる理由は、コンプレッサーの仕組みやファンの回転音、設置環境など、さまざまな要因が重なって起こります。しかし、簡単な工夫や道具の使用、正しい設置方法などで音を軽減することは十分に可能です。静音性に優れたモデルに買い替えることで、ストレスのない快適な除湿生活が実現できます。
さらに、除湿器だけでなく、部屋全体の生活音のバランスや防音対策にも目を向けることで、トータルで快適な空間づくりができるようになります。「音」は目に見えないストレスですが、しっかり対策することで日々の生活がぐっと過ごしやすくなります。ぜひ、できることから取り入れてみてください。